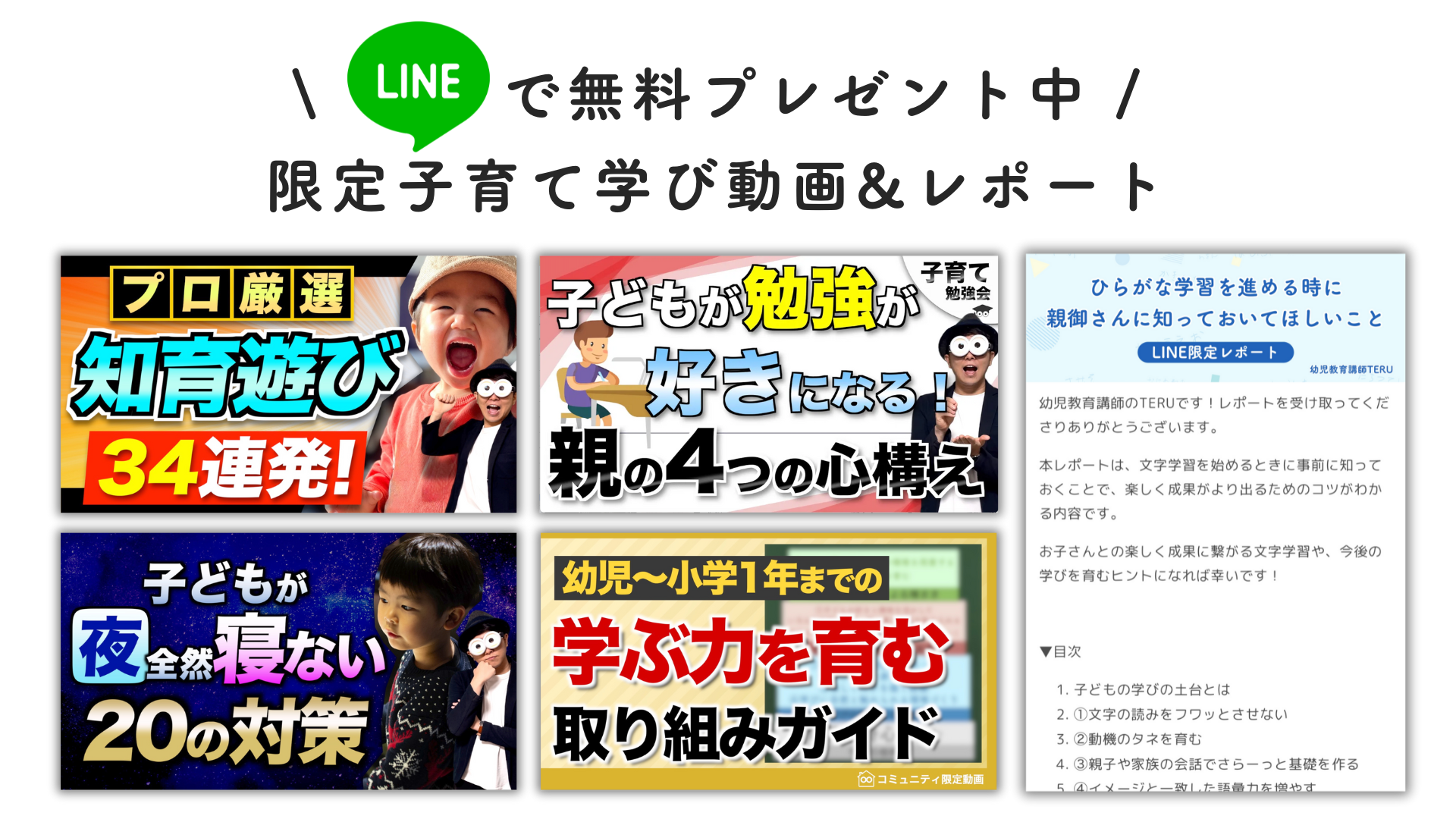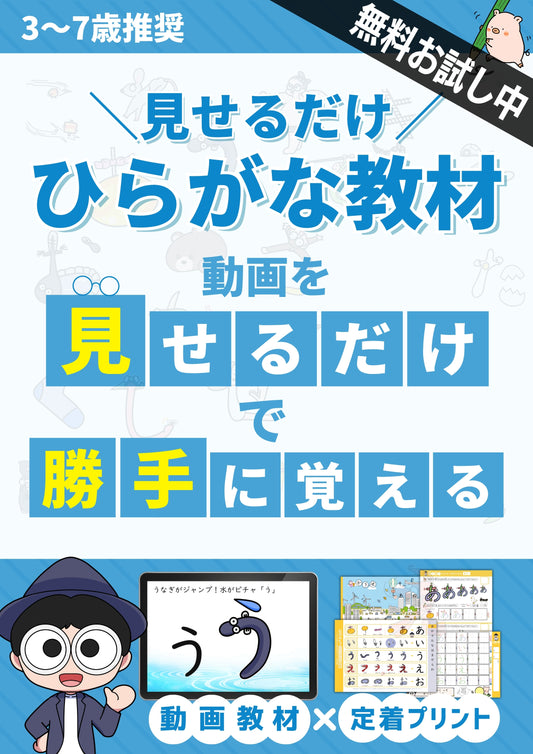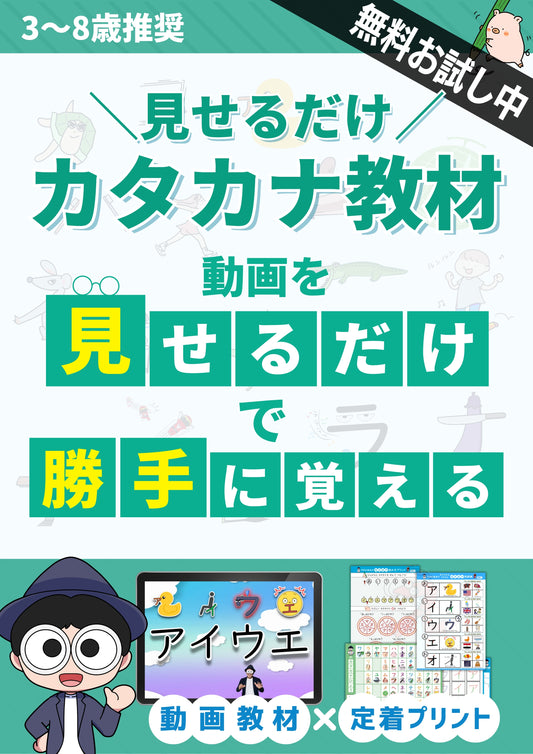「子どものやる気を高められる親になりたいです。まずは何から始めたら良いですか?」
これは多くの親御さんにとって関心ごとですよね。
これに関しては、まずは心理学で言う『やる気の3つの根本』を知るところから始めましょう!
解説していきますね!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
【目次】
- やる気の3つの根本
- やる気の根本①繋がっている感
- やる気の根本②できる感
- やる気の根本③自分から感じる
- ほとんど本質の話
- 【まとめ】「やる気」の先にあるもの
やる気の3つの根本
 やる気を高められる親でありたいと思ったとき「そもそもやる気ってどんな上がるの?」ということを正しく知らないと間違った考え方になってしまいます。
やる気を高められる親でありたいと思ったとき「そもそもやる気ってどんな上がるの?」ということを正しく知らないと間違った考え方になってしまいます。
これは心理学理論で「自己決定理論」と呼ばれるものですが、3人に分かれます。
- やる気の根本①繋がっている感
- やる気の根本②できる感
- やる気の根本③自分から感じる
この3つを感じる時、脳の快楽物質であるドーパミンが分泌され、その目標に向かって挑戦的に脳がデザインされていることがわかっています。
なるほど、子どものやる気を引き出していこうと思ったとき、この3つのどれかに注目を置いてアプローチをすると効果的だということですね!
さらに1つ1つ具体的に解説していきますね!
やる気の根本①繋がっている感
 簡単に言えば、誰かと一緒に何かをしたり、誰かのために行動したり、他の人と一緒に何かができそうだなと期待したりして「つながり」を感じるとドーパミンが出るわけですね!
簡単に言えば、誰かと一緒に何かをしたり、誰かのために行動したり、他の人と一緒に何かができそうだなと期待したりして「つながり」を感じるとドーパミンが出るわけですね!
具体的なシーンっていうと
- お片づけをしたことに対して「感謝の言葉」を受け取ったり
- ママと一緒に夕ご飯を作り共同作業で料理が完成したり
- この後、習い事で仲良しのAちゃんと会えることを想像したり
このような時に、やる気がグッと芽生えましたので。
彼にも
「お父さん今、〇〇で悩んでるんだけど、〇〇ちゃんだったらどうする?」
なんて、子どもを子ども扱いせずに頼るという行為もオススメです!対等に思ってもらっている感が、より繋がりを強く感じさせてくれます!
やる気の根本②できる感
 何かができたり、学べたり、達成できたとき、または、何かができそうだと予感したときに感じるのが「できる感」です。
何かができたり、学べたり、達成できたとき、または、何かができそうだと予感したときに感じるのが「できる感」です。
これはきっと説明はないと思いますが、いつか何かに挑戦して上手く行った「もう一度やりたい!」となるのはなんとなくわかりますよね。
ですので、よく「スモールステップな課題設定が大事」と言われるわけです。
簡単すぎてもやる気を出せる可能性があるので、良い塩梅の準備を整えてあげるのは大事ですけどね。
そして、「何かができるそうだと予感したとき」にもできる感覚を感じるのがポイントで、よくスポーツ選手が実際にやる前に先にイメージトレーニングをすると聞きますが、あれはその動きを再現するだけでなく、先に「できるイメージ」をすることで、自分のモチベーションを上げる効果もあるわけです!
それを子どもに応用したら、何かに挑戦する前に、何度も見る機会を作ってあげたり、スポーツであれば、プロの選手の試合を楽しく見ても良いですし、あとは、習い事で実際にそのスポーツをやる前に、まずはお家でライトに遊んでみてとか、できる感覚を作ってですね!
やる気の根本③自分から感じる
 これはもう説明はいりませんよね。自分から始める事や自分で決める事に対してはやる気が湧きやすいものです。
これはもう説明はいりませんよね。自分から始める事や自分で決める事に対してはやる気が湧きやすいものです。
きっと皆さんも、皆さんが気に進まないものに対して
- どれからやるか順番を決めさせたり
- どれを使うかを決めさせたり
- 使う道具を一緒に買いに行ったり
- 何時から始めるのかを決めてもらったり
- 親が手伝うことを子どもに指定してもらったり
- いくつかの選択肢の中から選んでもらったり
- どこでやっても自分で決めたり
こんな感じで、上記は抽象的な表現をしましたが、あなたの意見にされたことはあると思います。
これで必ずやる気が出るわけではありませんが、自分で決める・選ぶことはやる気が出やすい関わり方であるのは間違いありません。
あは自分から「やりたい!」って言った時にやめないということは、やっぱり大事ですね。
手伝いでも、習い事でも何でも
から「やりたい!」って言った時にやらせてあげる
=間違いなく自分から感覚が最大化する タイミング感覚
ですので、かなり尊重してあげたのが、やる気の視点からは大事ですね。
どちらの現実問題を尊重して与えられることだけではないので、親側もできる限り範囲できるで、尊重できるものを尊重してあげてOKだと思います!
ほとんど本質の話
 ここまでやる気の話をしてきましたが、みんなは、子どものやる気に幻想を抱いてはいけないとも思います。
ここまでやる気の話をしてきましたが、みんなは、子どものやる気に幻想を抱いてはいけないとも思います。
- 事故が起きないように勉強を中々やらない時とか
- 習い事の課題に全然手を付けていないで他のことをやっている時とか
ああははは
- 何にも無気力で「これ頑張りたい!」と思うものが無いという場合
また、わが子にやる気を出してほしいと願いません。
とりあえずとき、結局は実は「やる気を出してほしい」のではなく「行動をしてほしい」がだと思います。
やる気がなくても、「勉強は大変だなぁ。やる気が湧かないなぁ。でも勉強は自分のために必要だからやらないといけないな!」と思って行動をしてくれたら、やっぱりですよね。
だから、みんなはやる気に思わしすぎないことが大事だと思います。
とりあえず「やる気があるからやる」「やる気がないからやらない」という価値観が危ないことは大人の世界でもよく言われますよね。
ずっと人間的にやる気でいられる人なんていなくて、やる気に頼って何かを継続しようと思うと、多くの場合挫折します。
そうですね、やる気にはなれなくても、面倒なことや嫌なことや難しいことに対して行動できるようになれたら最高なのです。
そして、子どもがありそうな重要な要素の1つが「成長マインドセット」を育むことと言われます。
成長マインドセットとは、一言で言えば
「自分の能力は、生まれつき決まっているのではなく、努力や経験によって伸びることができる」と信じる心の在り方です。
これは、スタンフォード大学の心理学教授であるキャロル・S・ドゥエック博士によって提唱された概念で、「しなやかマインドセット」とも呼ばれます。
ここでこの成長マインドセットの育み方を話していると残っても消えてしまうので、以前以下の記事で解説したので、ぜひご覧いただけると嬉しいです!
【まとめ】「やる気」の先にあるもの
ということで、以上が、やる気の3つの根本的な話と、やる気に思われすぎない方がいいというお話でした!
- やる気の3つの根本:①誰かと繋がっていると感じる「つながり感」、②達成感や成長を感じる「できる感」、③自分で決めていると感じる「自分から感」。
- 親の役割:この3つの感覚を子どもが安心できるように、感謝を伝えたり、小さな成功体験を積ませたり、選択させたりするアプローチが有効です。
- 最も本質的なこと:やる気に頼らなくても行動できる力を育むこと。その鍵が「自分の能力は努力で伸ばせる」と信じる「成長マインドセット」。
- 結論:「やる気を出す」ことだけを考えず、長期的な視点で「やる気に頼らず行動できる力」を育てていくことが大切です。
とりあえずでもヒントになる部分があれば嬉しいです!
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。