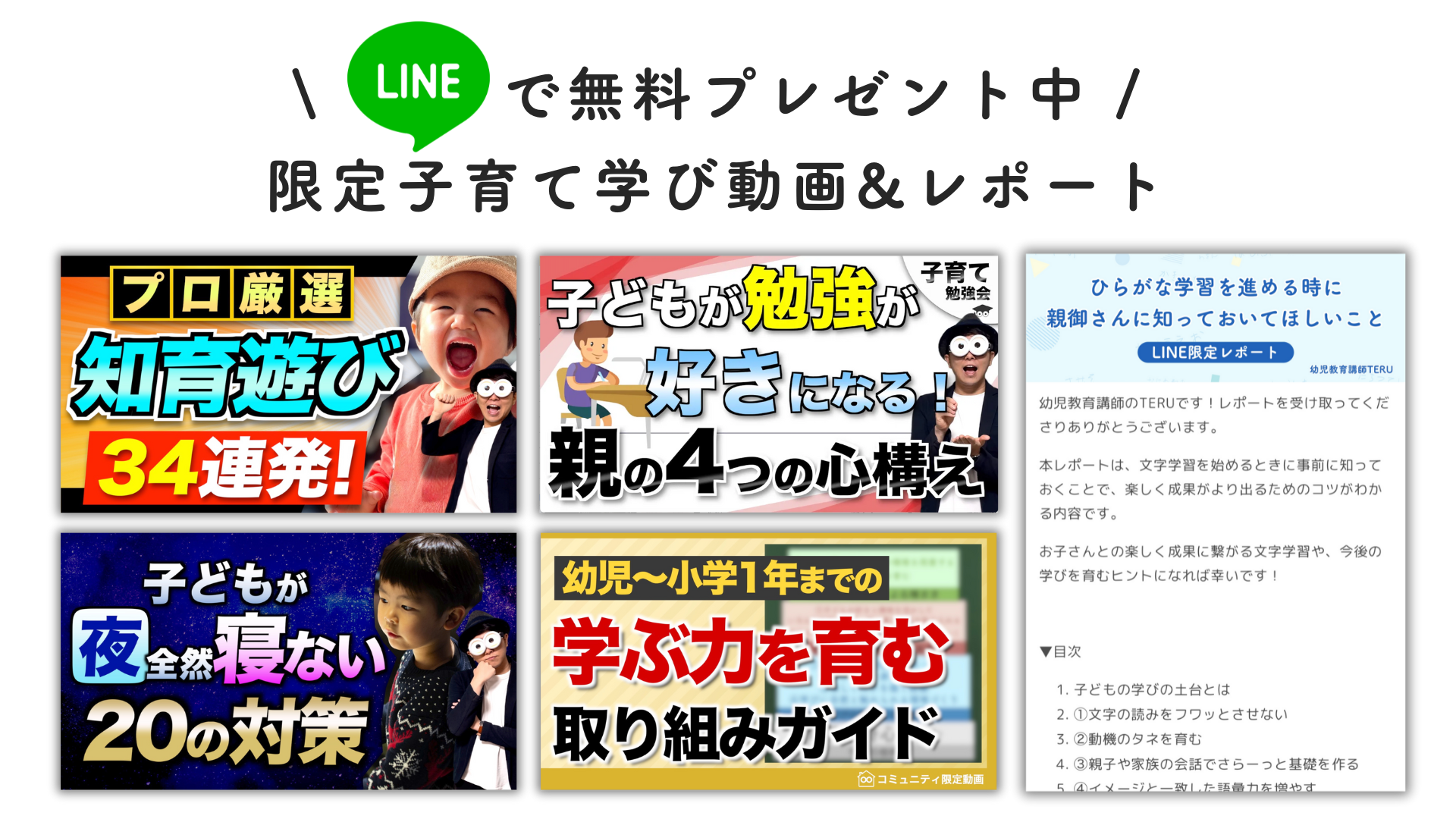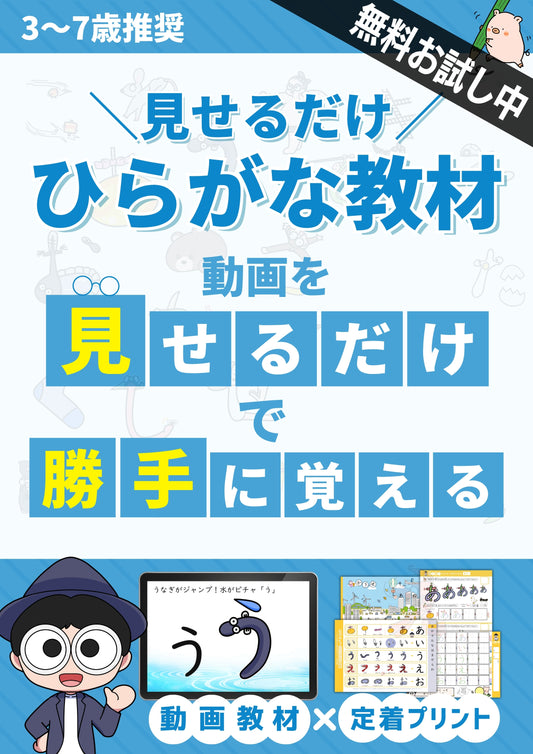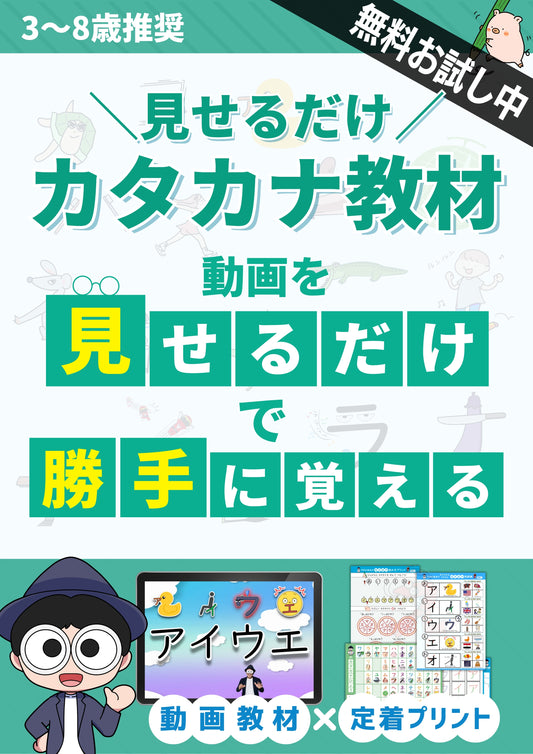今日は『子どものやる気』をテーマに、巷でよく聞ける親御さんからの質問10個に、一問一答形式で私の考えをお話ししていきます!
今後、子どもがやる気を持っていろいろ考えてくれたら多くの問題は解決してしまいますよね! そんな子育ての根幹のお悩みのヒントようになる心を込めてお話しさせていただきます。
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
1~12歳【厳選】子どものやる気を引き出すヒント10選 / 子育て勉強会TERUchよりQ1:やる気を出す親のスタンスに特徴はありますか?
 パッと挙げると「「今すぐ」にこだわりすぎていない」ことかなと思います。 やる気はいろんなきっかけや子どもになりのタイミングがあって生まれるものです。 多くの場合、子どもにやる気がないのではなく、子どものタイミングを大人が待ってないばかりに、ミスマッチが起きてしまいます。
パッと挙げると「「今すぐ」にこだわりすぎていない」ことかなと思います。 やる気はいろんなきっかけや子どもになりのタイミングがあって生まれるものです。 多くの場合、子どもにやる気がないのではなく、子どものタイミングを大人が待ってないばかりに、ミスマッチが起きてしまいます。
誰かに促進された場合より、なんかわかんないけど謎のタイミングやきっかけで自ら「やろうかな」と思った場合の方がやっぱりやる気ある行動ができることが多いと思うんですよね。
Q2: 周りの子と比べてアクティブに頑張れません。
このお気持ち、本当によくわかります。まずは着手したいのが『表面的にわかりやすく見える姿=やる気ではないかもしれませんね』という問いかけです。
例、何もせずにジーっと周りのお友達を見ている子がいるとします。 もしかしたらもしかしたら頭の中で「自分だったらこうな」とか色々な思考を巡らせているかもしれません。
Q3:子どものやる気に親の姿は影響しますか?
 【影響はある。でも親の姿だけで子どもはやる気になる!は安易すぎる】 と言っているが僕の所感です。
【影響はある。でも親の姿だけで子どもはやる気になる!は安易すぎる】 と言っているが僕の所感です。
ただ、今度親がいろんな良い姿を見せたり良い言葉を使っていれば子どもはやる気になるのか?というと、ちょっとがやる気の条件ではないですよね。
Q4:やる気を引き出すために最も意識していることは?
最もと言うと【なんとなく小さなできた!を経験させてあげるか】を意識しているかなと思います。
こんな感じで、全部成功したり勝つわけではないけど、負けや失敗をしすぎないというコントロールはやっぱり大事だなって思っています。現代では、安易に「失敗は経験だ!」という人がいますが、失敗から立ち直るくらいの経験と自信がない子に失敗ばかりさせれば、当初の自己有効感が揺らいでしまうこともあります。
Q5:本質的にやる気を持って使える子に育つには?
 これ、大事な問いですね。結論『自分で意図して行動した成功体験』だと思いますね。 さらに、こうやって自分の行動やアプローチによって結果が変わることを経験していたと、根本的な自己有効感の向上につながっていますよね。
これ、大事な問いですね。結論『自分で意図して行動した成功体験』だと思いますね。 さらに、こうやって自分の行動やアプローチによって結果が変わることを経験していたと、根本的な自己有効感の向上につながっていますよね。
この経験を選ぶのにオススメの方法は2つです。
- 何かを始める前に戦略を考えよう考えて提起:何かを始める前に「どんな戦略・作戦で取り組むか?」と課題を与えて、自分なりの方法を考えてから始める習慣を育んであげようということですね!
- 成功した理由を考えさせる:何かがうまくいったということで、多くの場合うまくいった理由があります。それを考えさせてあげることで「こうやったら上手くいきやすいんだ!」という気づきになり、結果として、次の作戦を立てていきますね!
Q6:勉強の間違いを指摘されるとやる気がなくなります。どう工夫すれば良いですか?
これは多くの方が悩まされているかもしれませんね。5つの工夫をあげます。
- 罰をつけない:×はつけず◯だけつけて、間違えたところは「悔しいから一緒に考えよう!」とサポートしながら最後は◯してあげます。
- 伝え方を工夫する:例えば「これは間違ってるね」と言われるより「ここ、よく考えられてるね!いいね!ここは後ちょっとだね一緒に考えてみようか!」みたいな感じで、まず良いところを伝えてあげる。
- 間違いの良さをセットで伝える:「間違った部分ってすごく大事だよね! 一度間違えたら、それを一生懸命考えてできるようにすればどんどん成長できるね!」などと皆さんの言葉で良い意味を伝えて上げます。
- 間違いを違う呼び方にする:間違いを「今日の伸び代」と表現して、「成長のチャンスだね!」という言葉と共に渡してあげる。
- お互いに間違いを見つける仕組みを取り入れる:親もわざと明らかに間違えた箇所を作り、それをお互いに指摘するようにすることで、自分の間違いも受け入れやすくなる。
Q7:子どもを叱ってばかりです。やる気がなくなるのが悩みです。
 私、行ったときの大事な確認ポイントが1つあると思っていてそうです、それは『良くない行動のときは叱られるのに良い行動や改善したときは何も言ってももらえない』という状況になっていないか?
私、行ったときの大事な確認ポイントが1つあると思っていてそうです、それは『良くない行動のときは叱られるのに良い行動や改善したときは何も言ってももらえない』という状況になっていないか?
大人側ができることは『叱られたことを叱られたままにしない』ということです。 叱られたことに関して、思い出していてそれを改善したときや、良い行動ができたときも気づいてあげています。
このような関わり方が、次の行動につながる意欲が湧く関わり方だと私は思います!
Q8:TERU先生は子どものやる気が出る環境ってどんな環境だと思いますか?
最も重要だと思うのは『周囲の当たり前レベルが高い環境』だと思いますよね。例えば、勉強にやる気を持って続けてください!欲しいと思いますよね。
そうしたら子どもは高確率で宿題などを始めると思います。 これが『周囲の当たり前レベルが高い環境』です。
- 親も一緒に勉強する
- 図書館を活用する
- 塾の自習室などを利用する
これらはやはり『周囲の当たり前レベルが高い環境』であり、やる気が出やすい環境ですよね!
Q9:勉強を親が教えるとやる気が下がります。どうしたら良いですか?
 これはまぁ色々正直あるんだけど、1つ盲点であることが多いのが『表情』なんですよね。上手な教え方とか、声かけの仕方とか、褒め方とか、きっといろんなことを考えながら子供と接していると思うのですが、一応意識が向かいすぎている結果『顔がとにかく怖い』親御さん実はかなり多いんですよね笑
これはまぁ色々正直あるんだけど、1つ盲点であることが多いのが『表情』なんですよね。上手な教え方とか、声かけの仕方とか、褒め方とか、きっといろんなことを考えながら子供と接していると思うのですが、一応意識が向かいすぎている結果『顔がとにかく怖い』親御さん実はかなり多いんですよね笑
真剣に言いたいと思っているからだと思うのですが、子どもはやっぱり楽しいのが好きであることが多く、笑顔ではなくても、優しい表情で接してあげても、勉強時間のイメージがちょっと変わったりするんですよね。
Q10: 褒められるのがうまく行かなかったり嫌われたり。
これ、年齢や皆さんの気質にもよりますが結構ありますよね。そんな時私がオススメしたい方法は『間接褒め』ですね。具体的には2つあります。
1. 周りにお子さんの頑張りを伝えて、その人からお子さんに伝えてもらう:例えば、旦那さんに「今日〇〇ちゃんこんなこと頑張ってすごかったんだよ!」と伝え、旦那さんからお子さんに「ママから聞いたよ!〇〇は頑張ってたんだってね!ママすごく喜んでたよー!」と伝えてもらいます。
2. 紙に書いて壁に貼る:みんなが一生懸命頑張っている姿を写真に撮って、そこに一言メッセージで良いので「シュートの練習を何度も何度も頑張ってすごかった!」と書いてください。口で褒められるのは頑張ってもらえるかも知れませんね!
【まとめ】本質的なやる気を育むために
ということで、今回の質問を振り返って、本質的な意欲を育むための核的なポイントをまとめます。
- 待つ:「今すぐ」を求めず、子どもが自ら「やろうかな」と思うタイミングを待っている親であること。
- 成功体験:小さな「できた!」を意図的に経験させるために、困難を調整し、成功の「戦略」を子ども自身に考えさせます。
- 否定の変換:間違いを「伸び代」と呼び、叱った後には必ず良い行動を認めて、叱りっぱなしに関わらない方を徹底する。
- 環境:周りの当たり前レベルが高い環境(親も一緒に勉強するなど)を作り、教える際は優しい表情を心がける。
ぜひ、できる限りできる範囲で、このヒントをご活用いただければ思います!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
幼児教育講師TERUでした。