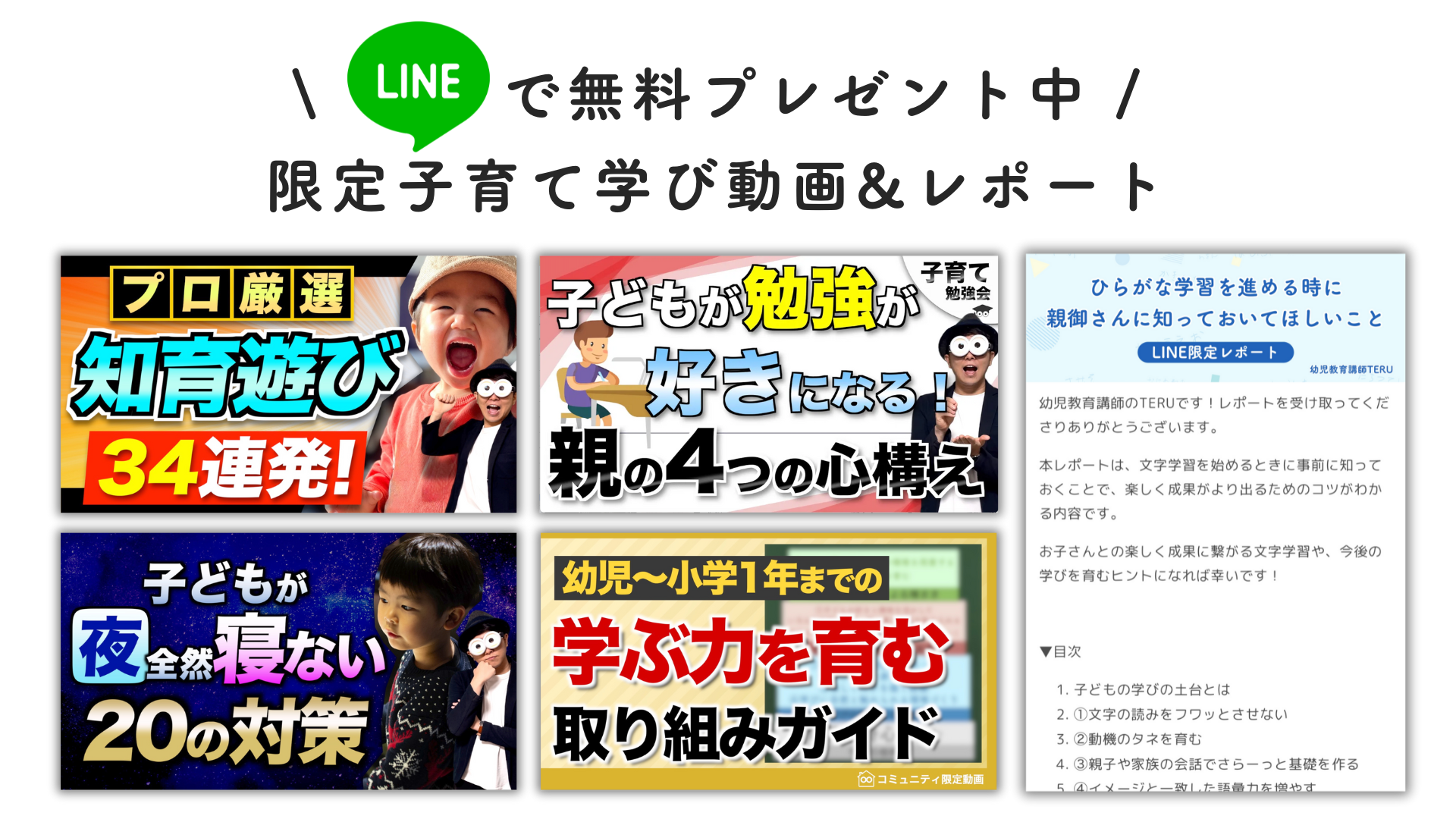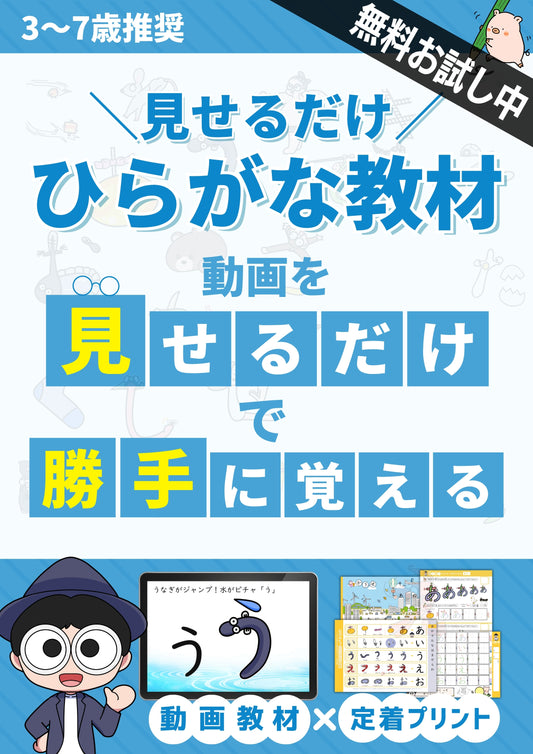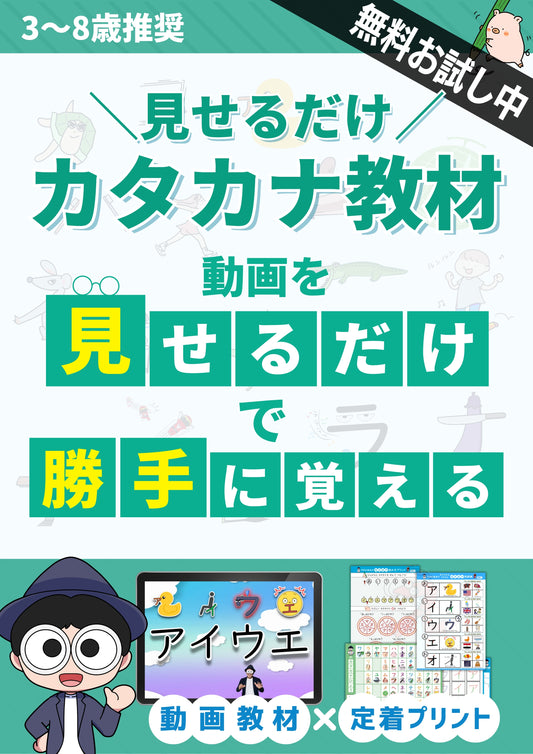「子どもが勉強や習い事など全部継続ができません。どうしたらいいですか?」
これは非常に難しい問題ですが、心理学から見て、1つ大事なことがあるのでご紹介してみたいと思います!
※ちょっと長いですが、3)と4)は特に大事だと思っているのでご覧いただけると嬉しいです!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
1~9歳【研究でわかった】子どもが諦めずにやり抜くことができるようになる4つの親の関わり方 / 子育て勉強会TERUchより【目次】
- それでも継続できない理由
- 親が気をつけたい「ある行動」
- 内発的な動機につながる声かけ
- 勉強をしているときにつきあげたい言葉
- 【まとめ】「ご褒美」より「感謝」で内発的な動機を育む
それでも継続できない理由
 人間が継続できない理由の1つとして心理学でよく言われるのは『内発的動機がないから』ということですね。
人間が継続できない理由の1つとして心理学でよく言われるのは『内発的動機がないから』ということですね。
きっと詳しい方も多いと思いますが、一応説明しますね!
▼内発的動機
外からの評価や報酬がなくても、興味・好奇心・やりがいといった内側から湧く気持ちを原動力に行動することをに向かいます。
▼外発的動機
外からの指示やごほうび・評価・罰といった取り組みによって、ご褒美をGETしたい、叱られることを回避したい、など「外的な結果」を目的に行動することを歩みます。
今年の心理学研究では、
内発的動機=持続がしやすい
外発的動機=瞬発力はあるもの、なかなか持続はしにくいという認識で
、
確かに、どこか内部発の動機を原動力にして解決になるかが、子どもが何かを続ける上では極めて重要なわけですね。
言ってみれば、これがまあ難しいんですよね。
親が気をつけたい「ある行動」
 この内発的な動機を考えた時、親が気をつけたい1つの視点としては
この内発的な動機を考えた時、親が気をつけたい1つの視点としては
「わざわざ内発的な動機が働いているのに、外発的な動機を後からかぶせえないように気をつける」ということですね。
例:子どもが自ら「お手伝いをしたい!」と話しかけます。
その時の子どもは「何かお駄賃が欲しい」とか「褒めて欲しい」とかという動機よりも
- 「親が洗濯物を畳んでいるのが面白いそう」
- 「洗濯バサミから洋服以後行為が面白いそう」
など、何か内から出る興味・好奇心が多かれ少なかれ賭けます。
あともう外発的な動機でお手伝いをしようと考えている場合は別ですけどね
それは置いてあります、
私たちは、その「お手伝いをしたい」という気持ちが嬉しいので、お手伝い中に大げさ「すごい!上手!」とか言ってみたり、場合によってはお駄賃をあげたり、何かご褒美にお菓子を買ったりしたりすることがあると思います。
これが戦う
『内発的動機が外発的動機に変わって起こる関わり方』の1つなわけです。
このような関わり方が頻繁になってしまうと、いつしか
- お菓子を買ってくれない手伝いをしない
- 褒められる人がいないと行動しない
こんな価値観になりやすいのは、皆さんもイメージができることかと思います。
ですので、今のような場面では、
「ありがとう。助かったよ」というようにさらっと感謝を伝えるくらいがちょうど良いですね
内発的な動機につながる声かけ
 ここまでの話で気になった方もいるかも知れませんが『感謝を伝える』主観、見方によっては外発的な動機付けだと思います。
ここまでの話で気になった方もいるかも知れませんが『感謝を伝える』主観、見方によっては外発的な動機付けだと思います。
ただ、他の外発的な動機づけと『感謝を伝える』ことの違いが1つあってですね。
それは
感謝を伝える
=人の役に立ちたいという喜びを感じる機会になる
ということです。
人の役に立つ喜びは、人の原動力として極めてパワーの強いものだと言われます。
それをご家庭の中で、人のために動いて感謝の言葉をもらったことで覚悟していることは、長期的な内発的動機を育てるのに極めて重要な関わりです。
こんな感じで長くなりましたが、まずは
- 内発的な動機に外発的な動機をかぶれないように気をつける
- 褒めるよりも感謝を伝えることを優先する
これは、子どもの内発的動機を阻害しないためのバランスの良い関わり方だと思います。
勉強をしているときにつきあげたい言葉
 たとえば、子どもが勉強頑張っているとします。その時も同じで、外発的動機に関わることが増えれば内発的動機とスイッチしてしまうことが起こります。
たとえば、子どもが勉強頑張っているとします。その時も同じで、外発的動機に関わることが増えれば内発的動機とスイッチしてしまうことが起こります。
でも、何か声をかけてあげたいという時はないですか。
こんな時私がオススメなの
「〇〇君が頑張っているので、お母さんも頑張ると思いました」
と、子どもの頑張りが周りにも良い影響を与えていることを伝えていくことです。
例
「〇〇君、勉強頑張ってるね、〇〇君が頑張ってるの見てと、お母さんも頑張ろうって思ってよ。よし、勉強のために読んで考えてた本をお母さんも読んでもうかな」
こんな感じの伝え方ですね。
これも先程の感謝の話に近いですが、自分の行動が褒められたのではなく、自分の行動が周囲に良い影響を与えているということを教えて声かけです。
こんな感じで、内発的な動機が外発的な動機にならないように気をつけながら、もし声をかけていれば、『感謝』や『周囲に良い影響を与えていること』を伝えます。
ぜひそんなことを意識して受け取っていいんじゃないかと思います!
よく言われる
・結果よりプロセスを褒める・
工夫を褒める
ような褒め方も子どもの将来の成功に最も影響があると言われる『成長マインドセット』を育むために有効なので、ぜひやってあげてくださいね。
【まとめ】「ご褒美」より「感謝」で内発的な動機を育む
ということで、子どもが何かを続けられない理由の1つとして、内発的動機と外発的動機の話をしてきました。
- 継続の鍵は「内発的動機」:ごや罰のため(外発的)ではなく、「やりたいからやる」気持ちが大切です。
- 親のNG行動:「やりたい」気持ちで始めたことに、後からご褒美や過剰な賞賛(外発的動機)を受け取った事。
- 効果的な声かけ①「感謝」:「ありがとう、助かったよ」と伝えることで、「人の役に立つ喜び」という強力な内発的動機を育む。
- 効果的な声かけ②「良い影響」:「あなたが頑張っている姿を見て、私も頑張っているつもりだと思います」と伝え、自分の行動の価値を実感させます。
ただこれだけが子どもの行動が続かない原因ではありませんが、何かヒントになる部分があれば嬉しいです
さて、先ほど出てきた『成長マインドセット』に関しては
・子どものやり切る力や・
自ら始めて成長していく力の根本
だと最近の研究でわかっています。
最近私は、子どもの成長マインドセットを育むための子ども向けのコンテンツ作りに非常に力を入れています。
もしご興味がある方は、僕が運営するオンラインで子ども向け教材が使いたい無制限のTERU先生の動画教室にも遊びに来ていただけると嬉しいです
▼詳細はこちらから
https://lit.link/terukyoiku
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました
日々子育て、本当にお疲れ様です!