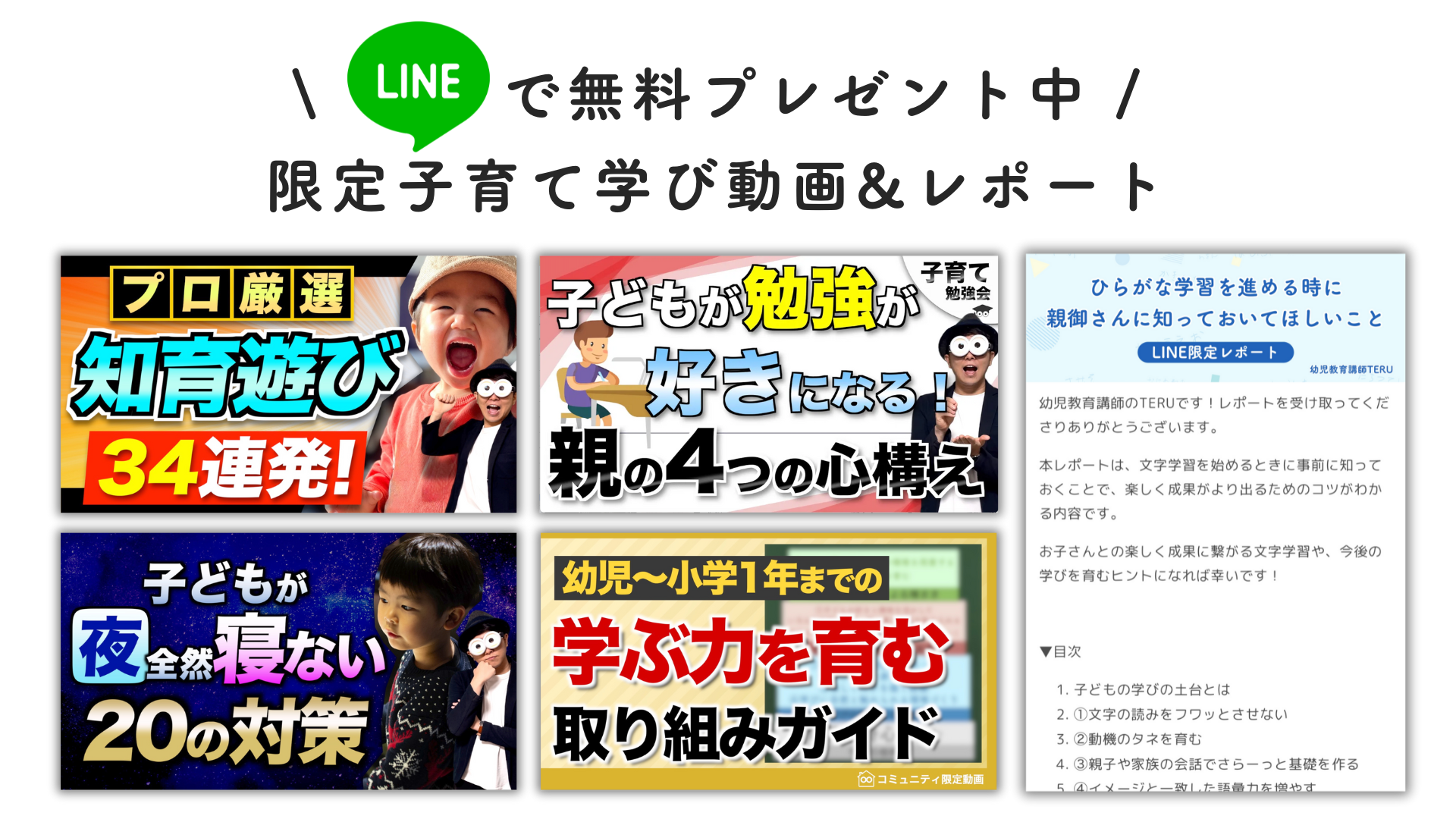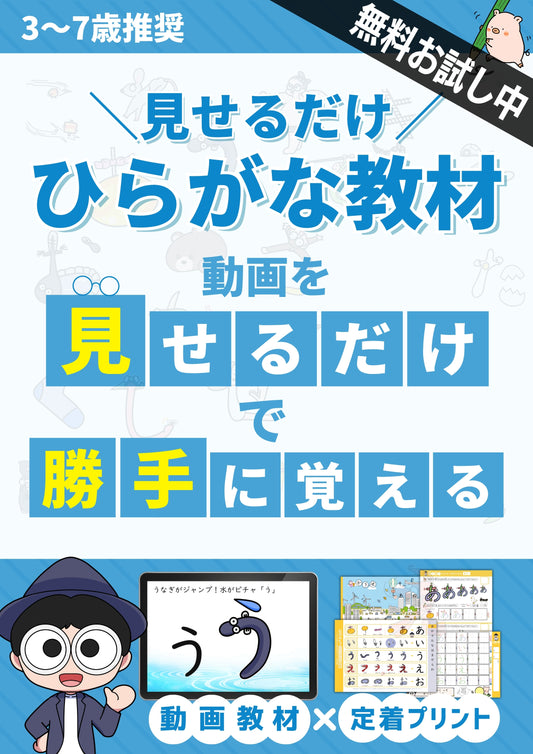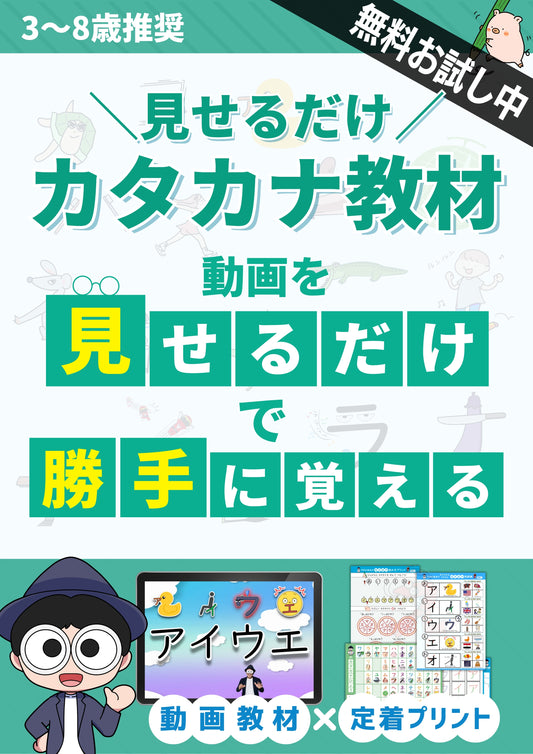これから子どもたちが生きていく時代。今の私たちが生きる現代より、より不確定な要素が多く、変化も早いのは間違いがありません。
こんな時代だからこそ『どんな環境でも挑戦できる』ということはものすごい強みになります。
今日は子どもが『どんな環境でも挑戦できる』ようになるために、私たちができることについてお話しさせていただきます!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
1~12歳【子どもの脳科学】挑戦できる強い脳を育む子育て / 子育て勉強会TERUchより【目次】
- 挑戦できる脳の土台「心理的安全性」とは?
- 鍵は「メタ認知」 - 自ら安全な心を動かす思考法
- 家庭でできる!メタ認知を育む3つのサポート
- 【まとめ】どんな時代でも負けない「強い脳」を育てる
挑戦できる脳の土台「心理的安全性」とは?
 進歩の成長に関しては「心理的安全性」が重要だと言われます。
進歩の成長に関しては「心理的安全性」が重要だと言われます。
人は心理的に安全な状態だと、脳の思考や感情をコントロールする部分がうまく機能し、能力を発揮しやすくなります。
しかし、子どもが何か苦手なことに対して何度も叱られるような環境にいれば、脳は「考え」だと学習し、思考を司る「前頭前野」の働きが抑制されてしまいます。その結果、自分をコントロールできなくなり、悪循環が生まれてしまいます。
ただし、大人が子どもに1から10まで安全な環境を膳を立てる必要はありません。 大切なのは、子ども自身がストレスのかかる状況を「自分で乗り越える力」を育むことです。
鍵は「メタ認知」 - 自ら安全な心を動かす思考法
 では、どうすれば良いのか。その鍵となるのが『メタ認知能力』です。
では、どうすれば良いのか。その鍵となるのが『メタ認知能力』です。
メタ認知能力とは、『自分を俯瞰的・客観的に見る能力』のこと。
この力があると、自分の心の動きを予測できるようになります。 そして、その予測したことを上手に言語化する力があれば、その結果として、自分をうまくコントロールできるようになっていきます。
例、自分がネガティブに陥りやすいパターン(「私はYouTubeの数字が気になると仕事が手につかなくなる」)を客観的に認識し、その上で「スマホをリビングに置く仕事部屋にこもる」といった具体的な対策が打てるようになること。
この思考習慣を繰り返していくと、どんな否定的な状況にも諦めたとしても心理的に安全な場を自分で判断できることができるようになるわけです。
家庭でできる!メタ認知を育む3つのサポート
 この思考習慣を育むために、私たち大人ができる具体的なサポートを3つご紹介します。
この思考習慣を育むために、私たち大人ができる具体的なサポートを3つご紹介します。
1. なんでうまくいったのか?を振り返る
まずは前向きな出来事から俯瞰して見て練習をします。
「おー!良い量だね!何でこんな良い量が取れたの?」と聞いてください。
この優しく関わって『良い結果には必ず理由がある』ということがわかってくると、『自分の行動で結果が変わる』という大切な感覚を信じることができます。これが挑戦する力の土台となります。
2. 頑張ったときのことをアルバムに文章とともに残す
特に、今まで苦手だった事に挑戦できた時は、その姿と方法を忘れないように記録に残しましょう。
例、自転車に初めて乗れた時、ぜひ写真を撮ってください。 そして、「なんで乗れるようになったのかな?」と聞いた答えを添えて記録に残します。
そのアルバム自体が、どうやってやっても挑戦すれば良いのか?という「解決策の引き出し」になります。
3. 何か苦手な場面の前に作戦を考えよう
皆さんがこれから苦手な場面に立って、「どんな作戦で乗り越える?」「どうしたらうまくいくかな?」と、自分なりの戦略を立てよう、想定してください。
1つの案だけでは心細くなりますが、2案、3案があることで、挑戦を支える勇気になってくださいます。この習慣が、困難にじっくり考えたときに自分で解決策を基盤となるわけです。
【まとめ】どんな時代でも負けない「強い脳」を育てる
今回は、子どもが「どんな環境でも挑戦できる強い脳」を育む方法についてお話しました。
- 土台の知識:心理的な安全性が重要であり、その安全性を自ら発生させる力こそが「メタ認知能力」である。
- 行動の鍵:親の役割は、子どもの行動をコントロールすることではなく、成功体験や失敗体験を通じて「自分の心のパターンを客観的に見て、対策を立てる」という思考習慣を教えること。
-
3つの実践:
- 成功した理由を「振り返る」。
- 頑張った記録をアルバムに「残す」。
- 苦手なことの前に「作戦会議」をする。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。