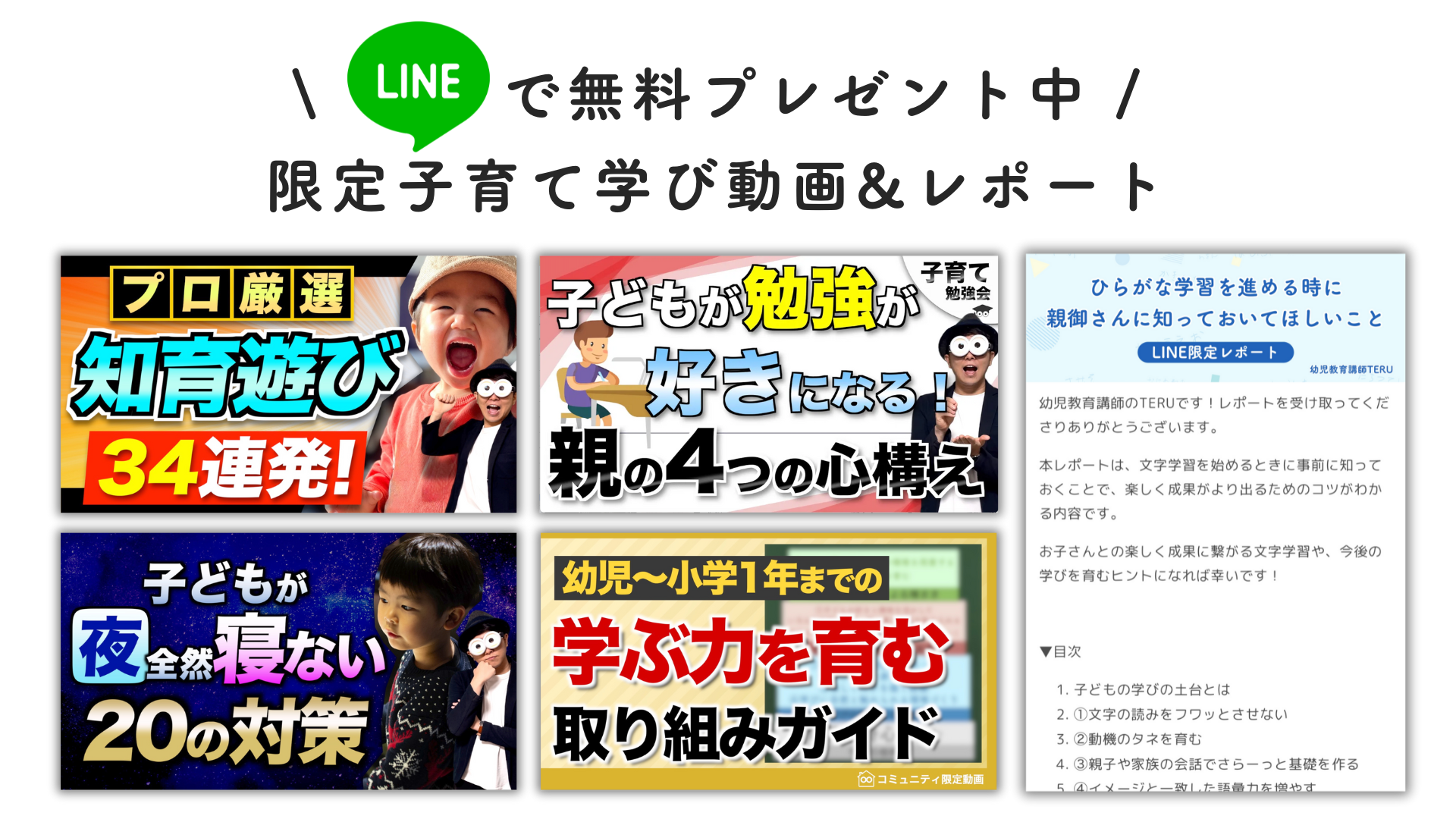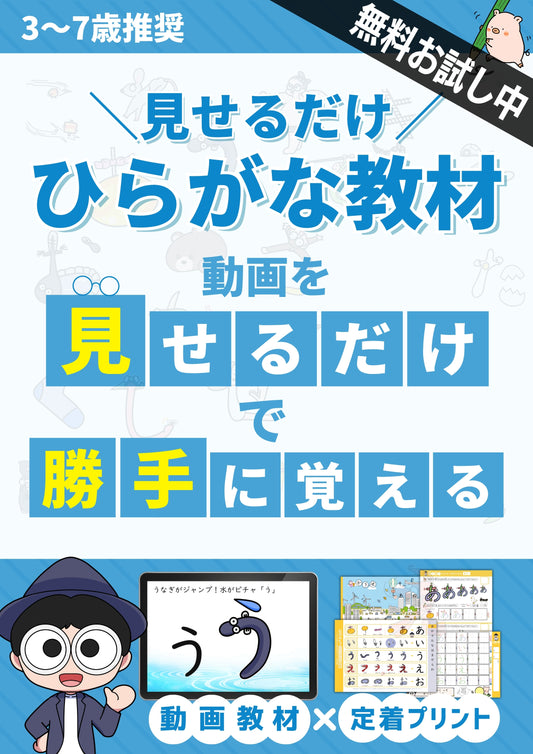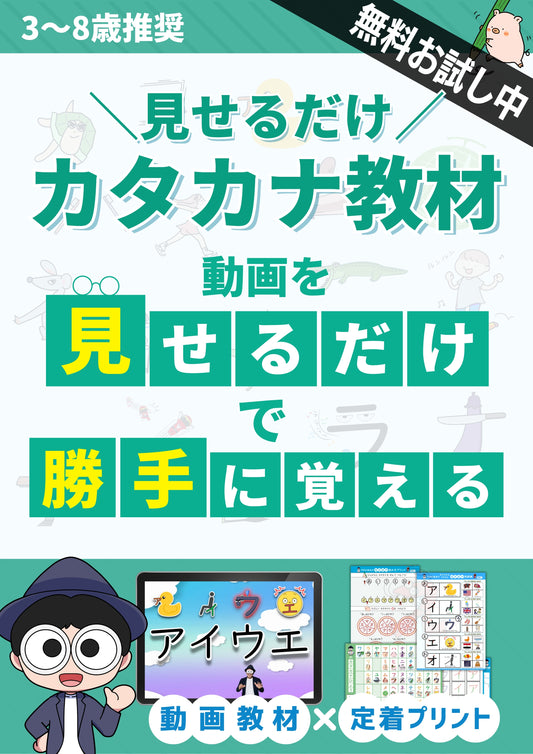幼児教育講師のTERUです。
「わが子が夜すぐに寝られるようになる方法ってありますか?」
これは多くの親御さんが気になる問いだと思います。
毎晩絶対にスッと眠れる!とまでは言い切れませんが、生理学の観点から大事な考え方があります。
【目次】
- 脳は「場所」と「行動」をセットで覚える
- この働きが“逆効果”になることもある
- 夜の「読み聞かせ」の注意点
- 寝つけないときの正しい対応とは?
↓この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちらの動画内で解説しています!
❶ 脳は「場所」と「行動」をセットで覚える

実は僕たちの脳には、「ある場所」と「そこで行った行動」をセットで覚える性質があります。
- キッチンに立つと料理モードに
- 勉強机に座ると学習モードに
というように、脳はその場所の経験を元に次の行動を準備するんですね。
この脳の性質を「フィードフォワード」と言います。
❷ この働きが“逆効果”になることもある

このフィードフォワード、実は睡眠にも大きく関係しています。
夜眠れずに、布団でゴロゴロして1時間以上過ごす
→ その結果、脳は「布団=起きている場所」と覚えてしまうのです。
すると次の日、
「さあ寝よう」とベッドに入っても…
脳が「ここは目を覚ましている場所だよ」と反応してしまう。
結果的に、寝つきにくくなってしまいます。これは、大人にも子どもにも起こる現象です。
❸ 夜の「読み聞かせ」の注意点

ここで、子育て中の皆さんにお伝えしたいのが2つの注意点。
まず1つ目が 「絵本の読み聞かせは布団の中でやらない」ことです。絵本タイムは最高の親子時間ですが、布団の中で読むと…
脳が「布団=お話を楽しむ場所」と覚えてしまう。つまり、寝床が“覚醒の場”として認識されてしまう可能性があるんですね。
■おすすめの流れ:
- リビングやソファで絵本を読む
- 「そろそろ眠くなってきたね」と声かけ
- 一緒に寝室へ移動して、布団に入る
こうすることで、「寝室=眠る場所」というイメージが、子どもの脳にしっかり刻まれていきます。
❹ 寝つけないときの正しい対応とは?

次に2つ目のポイント。
それが 「眠れないまま布団にとどまらない」 ということです。
人間の脳には、
「15分以上眠れないと、その後1時間は眠れなくなる」
という性質があります。
「眠れないけど、そのうち寝るでしょ」と布団に居続けると
→ 逆に脳が“起きている方向”に切り替わってしまうんです。
その結果、ますます眠れなくなるという悪循環になってしまうんですね。
■生理学的に正しい対応:
- 10〜15分寝つけなければ、思い切って布団を出る
- リビングで静かに絵本を読んだり、優しくお話したりする
- 「眠そうになってきたな」と感じたら、再度布団へ戻る
こうすることで、
- 「寝室=眠る場所」
- 「寝られないときは一度リセット」
という正しい脳のパターンが育っていきます。
【まとめ】
最初は親も大変です。夜中にベッドを出るのは正直しんどいですよね。
でも、脳のパターンが整えば、子ども自身の眠りの力が育っていくようになります。
- 「眠くなったらベッドに入る」
- 「ベッドに入ったらすぐ眠る」
この一連の行動が、“自然とできるようになる”脳の仕組みを、親が最初にサポートしてあげることが大切です。
できる限りできる範囲で、ぜひ実践してみてくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。