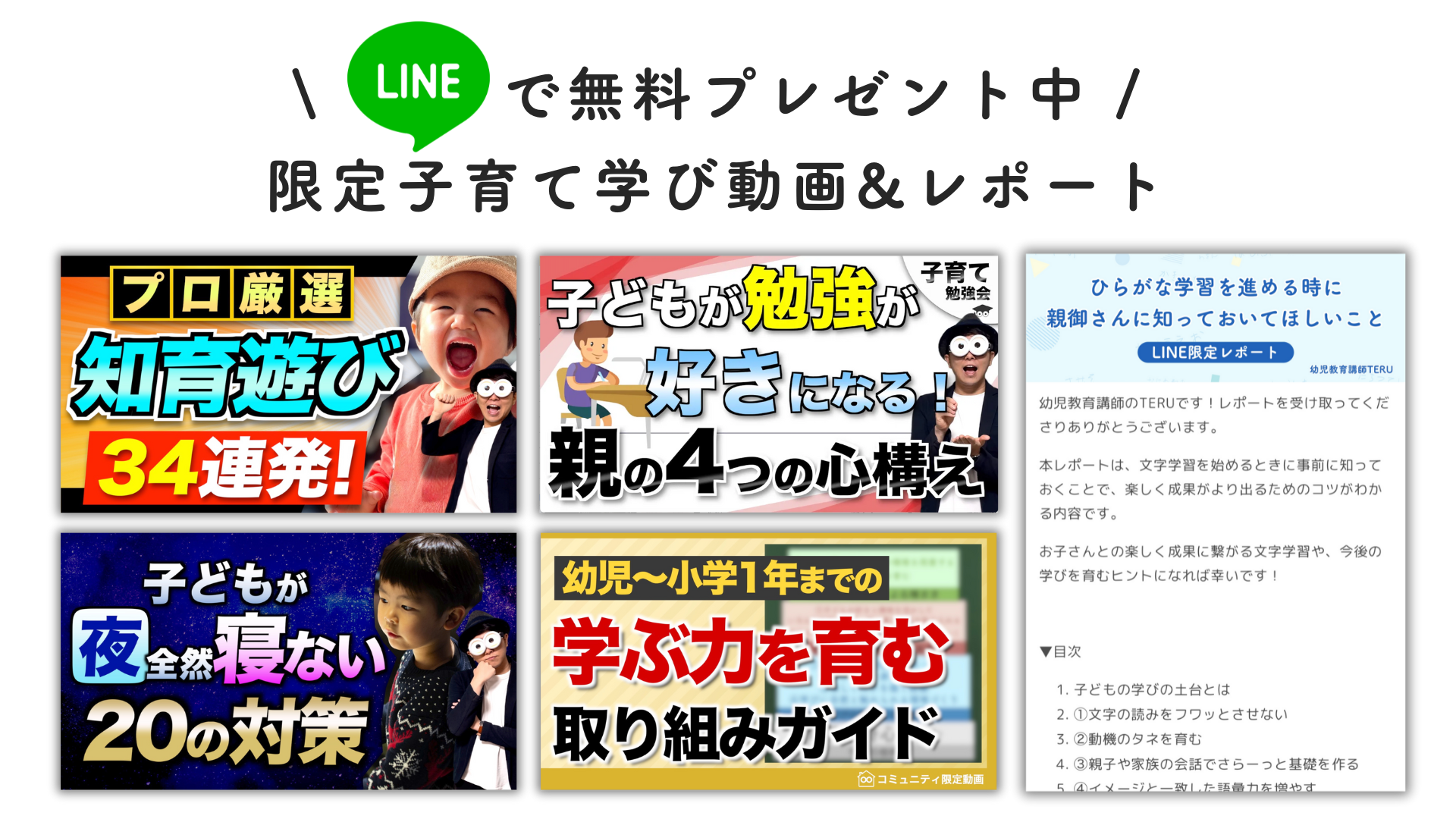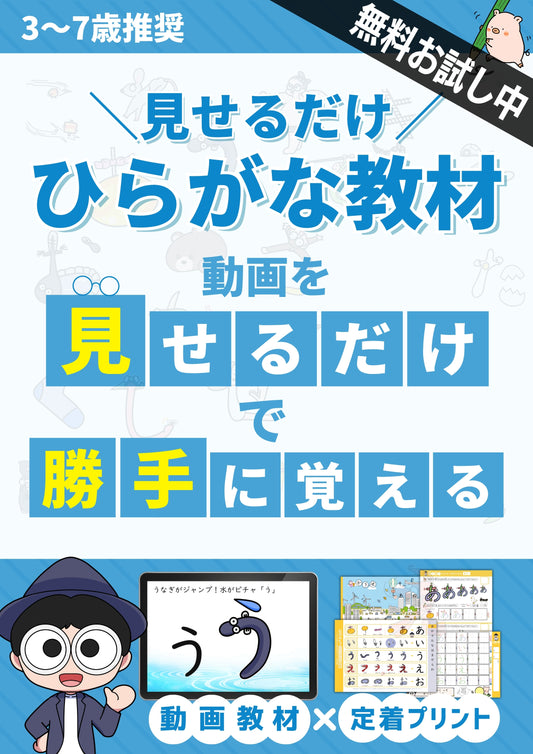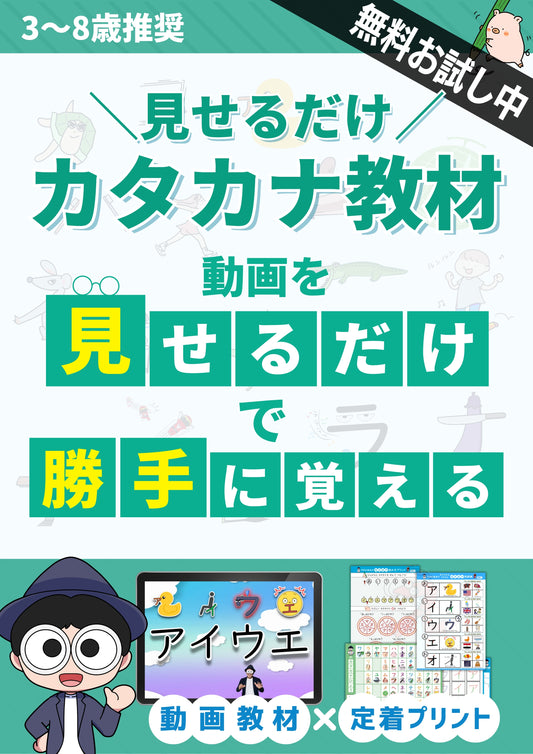6歳女の子の親御さんから以下のご質問をいただきました。
「漢字の書きについて、今までは形が合ってたらOKにしていたが、そろそろ書き順にも拘りたいです。横で見ていて、一文字書き終えたら注意するのですが、不機嫌になります。嫌いにならずに続けられる方法はありますか?」
3つ重要なことを紹介しますね
【目次】
- 前提
- 3つの原理原則
- 原則①書き順こそ事前のインプットと鉛筆を持たないアウトプットが大事
- 原則②書いた後に修正ではなく、書く前の意識づけがベスト
- 原則③自分からの気づきは成長の証なので承認しよう!
- 他にもいくつかポイントを挙げます!
- 【まとめ】「書く楽しさ」を守りながら、書き順を身につける
前提
 書き順をどこまでこだわるか?は本当にそれぞれの価値観。今は学校でもそこまでこだわりすぎない先生も多いし、テストで書き順は問われないことがほとんどです。
書き順をどこまでこだわるか?は本当にそれぞれの価値観。今は学校でもそこまでこだわりすぎない先生も多いし、テストで書き順は問われないことがほとんどです。
書き順よりも読める字を正しい形で書く方が重要度が高いので、書き順の優先順位はそこまで上げないという考え方もありますよね。
小学校低学年くらいまでは、まだまだそもそもの書く楽しさを育ててあげたい時期でもありますしね
なので、どこまで書き順を求めるか?完璧を求めるか?本当にひどいのだけを指摘するか?そもそも指摘しないか?は色んな価値観があっていいと思います。
その前提の上で、もし書き順にこだわる場合に親ができることという視点でお話ししていきたいと思います!
3つの原理原則
 今回のご相談にはいくつかポイントがあると感じました!まず最初に原理原則を書きます。
今回のご相談にはいくつかポイントがあると感じました!まず最初に原理原則を書きます。
- ①書き順こそ事前のインプットと鉛筆を持たないアウトプットが大事
- ②書いた後に修正ではなく、書く前の意識づけがベスト
- ③自分からの気づきは成長の証なので承認しよう!
この3つを大切にすると、お子さんが少しずつ書き順に意識を向けられるようになっていき、書き順通りに書けることが増えていくと思います
ここからさらに解説していきますね!
原則①書き順こそ事前のインプットと鉛筆を持たないアウトプットが大事
 これは、ご質問者さんはすでにされているので、ぜひ継続してあげてくださいという項目なのですが、
これは、ご質問者さんはすでにされているので、ぜひ継続してあげてくださいという項目なのですが、
書き順は、最初から書きながら覚えるって子どもにとって結構ストレスが多かったりするんですよね。
多分一般的には、読めたらどんどん書きましょう!書き順も一緒に練習!という感じだと思うのですが、形もうろ覚え、書き順も曖昧な中、書くのってすごく意識やワーキングメモリを使う行為で、そして、その上間違えたら指摘をされてしまうと、子どもにとって結構ダメージがデカいんですよね
なので、形も書き順もまずは書く前にインプットをぜひしてあげて欲しいと思っています。
このご質問者さんは、僕が運営するTERU先生の動画教室の中の、漢字動画を使ってくれているそうので、それでインプットをさらに続けて、まずは形と書き順を鉛筆を持たない中で続けていってあげて欲しいです
字の形と書き順のイメージに自信が出てから書き始めることで、ストレスが格段に減り、親御さんが指摘をしないといけない場面も少なくなると思います!
▼漢字教材を使ってみたいという方は、こちらのTERU先生の動画教室で使えます。
https://teru-education.com/pages/douga-kyoshitsu
原則②書いた後に修正ではなく、書く前の意識づけがベスト
 これは、ご質問者さんはすでに大事にされているかもしれませんが、書き順などに対して、親が何かしらのアプローチをするなら、書いた後より、書く前がより良いですね!
これは、ご質問者さんはすでに大事にされているかもしれませんが、書き順などに対して、親が何かしらのアプローチをするなら、書いた後より、書く前がより良いですね!
例えば、
・今日練習する漢字を先に書き順を一緒に確認したり
・親子で交互に指でなぞり書きをしたり
・この漢字はどこから書き出すのかな?とクイズ遊びをしたり
・お母さんの背中に漢字を書いて当てる遊びをして「書き順通りじゃないとお母さんわからないからお願いね!」とお願いするのも、書き順の意識づけになるのでいいですね!
なるべく遊びのような感覚を得られる事前確認の方法ができると、ドーパミンが分泌されて、記憶にも残りやすい状態になりますね!
と、書く前の話をしてきましたが、じゃあ書いた時に間違えたのは指摘しなくていいのか?という疑問が湧くと思います。
これは難しいんですよね
僕は、基本はとにかく「書くのが楽しい!」と思って終わることを優先するスタンスなので、書き順が違っても書いた後は指摘せずに、また次書く前に遊びを通じて正しい書き順の意識をさせたり、僕の漢字動画を使って、正しい書き順を楽しくインプットするのを繰り返すと思います。
ちなみに、動画を見ながら一緒に能動的になぞり書きをしたりはしなくてもOKで、見ているだけでも頭の中で書き順を考えていたりするので、指を一緒に動かしていないと意味がないと考えない方がいいですね!
これが僕の基本スタンスですが、一方で、そういったことを長く続けても、ずっと書き順を間違える漢字ってありますよね。
そのような漢字に関しては、何かしらのイメージを紐付けたインプットの仕方を工夫しますね!
例えば「火」を人から書いてしまうとします。正しい書き順をイメージに残すとしたら
「火ってさ、熱いじゃない?火がボッボッと着いたら人が熱い!!って言うよね!」だから、火の書き順はまず左のちょんと右のちょんが火のようにボッとついてから、人を書くのかもね!」
というように、形に紐づけた書き順のイメージで教えてみたり、
後は、リズム良く「火はちょんちょん人!」とリズム押しで教えるのもありですね!
お子さんと一緒にそんな感じのを作っても面白いかもしれません
そうやって、お子さんと書き順イメージで遊ぶことで、長期記憶に残りやすくなりますね!
いずれにせよ、できるだけ書く前の意識づけやインプットを大切にしてあげて欲しいなと思います
原則③自分からの気づきは成長の証なので承認しよう!
 ご質問者さんから、さらに以下の相談もいただきました。
ご質問者さんから、さらに以下の相談もいただきました。
2度書き(子ども自身が、バランスが悪いなと思った時に、一画だけ付け足す)も、たまに注意します。「突き出る・突き出さない」や「つける、つけない」も、このタイミングで教えたいのですがハードルが高いですか?
「二度書き」は成長の段階から見ると、結構良いこともあることは知っておけると良いなと思っています。
二度書きって、形が崩れたことに自分で気づいて、修正しようとする能動的な行為なんですよね。これは、脳の中で「お手本の字」と「自分の字」を比較して、間違いを見つける「自己モニタリング能力」が育っている証拠だったりします。
なので、注意をするというより、「あっ、今バランスが悪いって自分で気づいたんだね!良いね!」と、まずお子さんの「気づき」そのものを褒めてあげられると良いなと思ってます
二度書きが気になってしまう気持ちすごくわかりますけどね
他にもいくつかポイントを挙げます!
 ①一度に多くの文字の書き順に意識を向けるのは脳のキャパ的に難しいので、まずは1文字だけにフォーカスする
①一度に多くの文字の書き順に意識を向けるのは脳のキャパ的に難しいので、まずは1文字だけにフォーカスする
②そもそもの書き順に対して全くモチベーションが無いなら、書き順の大切さをちゃんと話しながら理解してもらう必要もある(どう伝えるか難しいですよねこれ)
代表的なのは
・書き順は手が一番疲れない順番だから覚えると得
・書き順が曖昧だと、どこから書こうかな?と毎回考えるので、脳が疲れるから書き順を覚えるとより疲れなくなる
とかですかね
③正解か間違いに縛られない世界線の時間が極端に少なくないか?もチェック
┗できたかできてないか、成功か失敗か、正解か不正解か。このように感じる取り組みが子どもが過ごす時間の多くの時間を締めていると、やはり間違いに敏感になりやすい。難しいけど、日頃の環境にも少し目を向けて、あまりにも◯×を感じる時間が多いと感じたら、環境を調整してあげるのも大事。
【まとめ】「書く楽しさ」を守りながら、書き順を身につける
ということで、以上、今回のご相談に対してお伝えしたかったことです!何か少しでもご参考になれば嬉しいです
- 前提:そもそも書き順にどこまでこだわるかは家庭それぞれでOK。書く楽しさが最優先。
- 原則①:書く前に動画やなぞり書きでインプットを徹底する。
- 原則②:書いた後の指摘より、書く前の意識づけをゲーム感覚で行う。
- 原則③:子ども自身の「二度書き」などの気づきは、成長の証としてまず承認する。
- その他:一度に1文字に絞る、書き順のメリットを伝える、○×のない時間を確保することも大切。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。