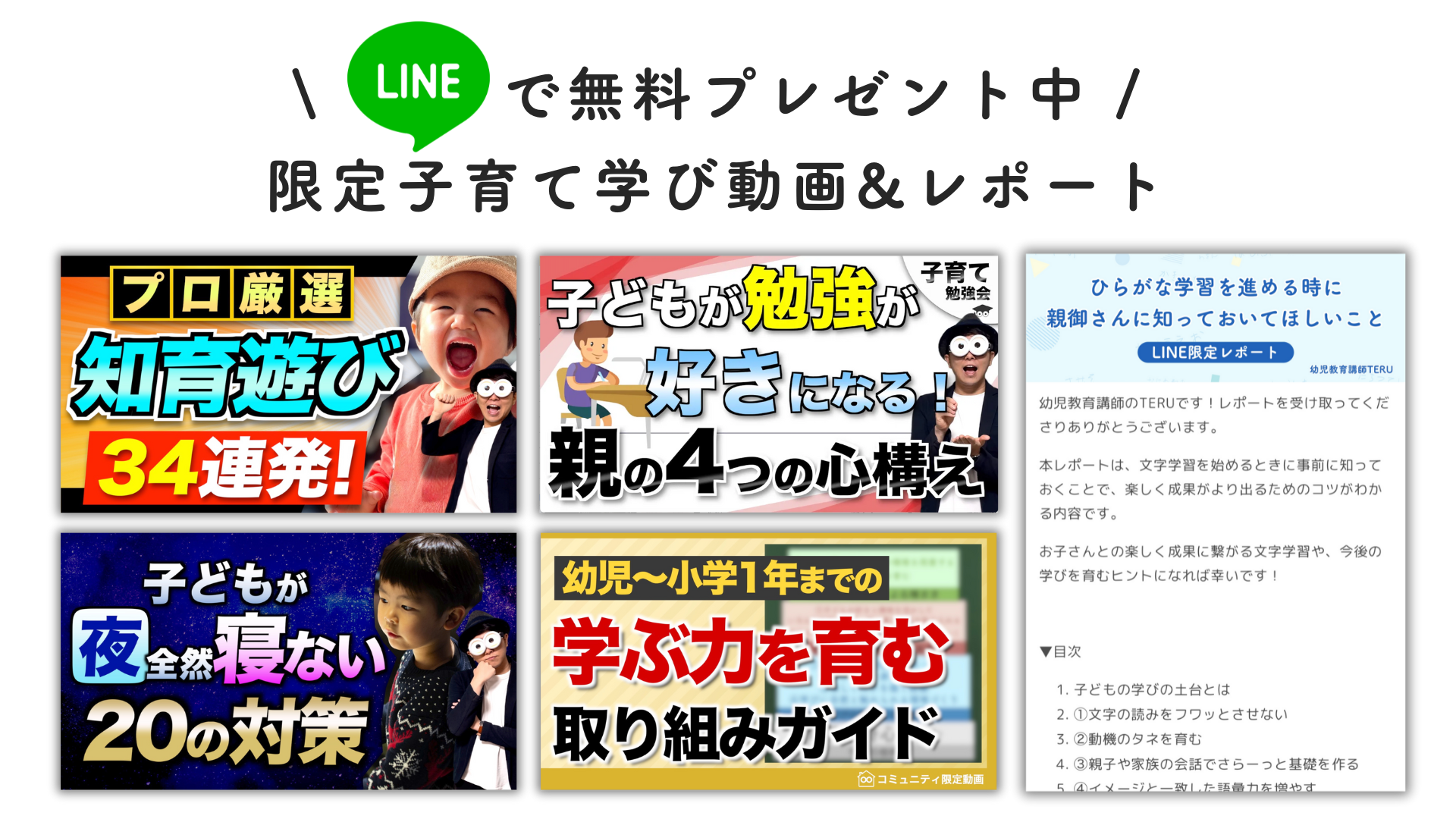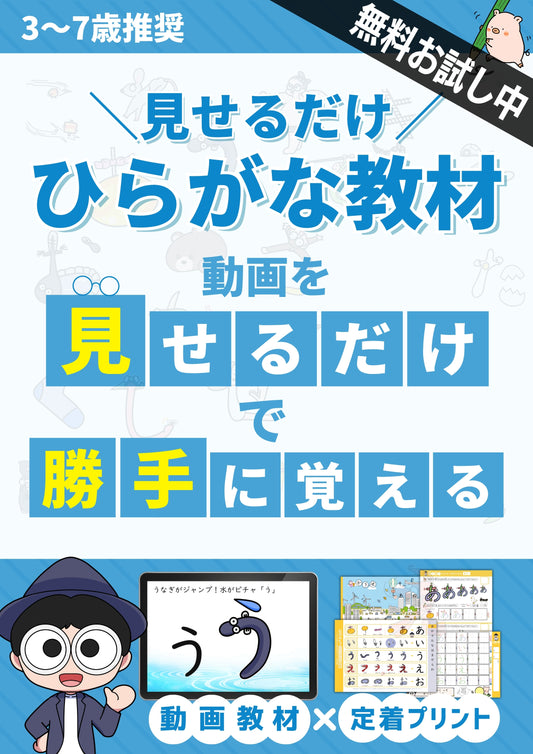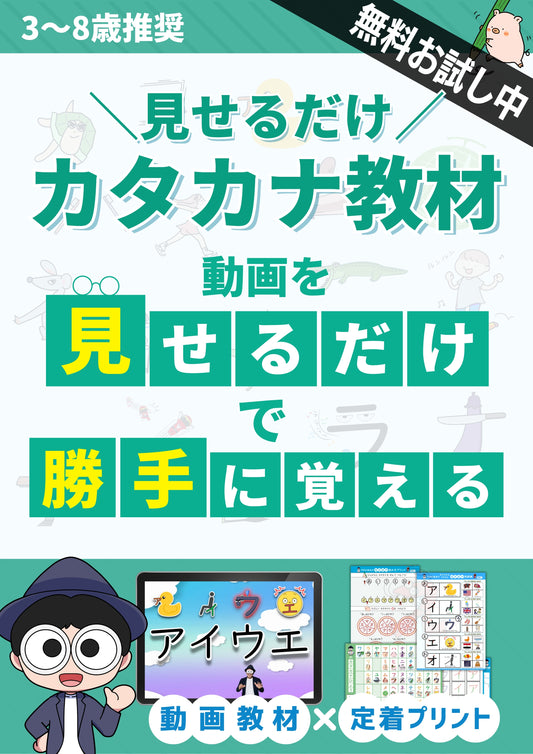「子どもが勝ち負けに異常にこだわって不安」 「自分には価値が無い!と強い気がしている」
こんな悩みを抱えているご家庭は多いのではないですか?
今回はそんな『勝ち負けの世界』『白黒の世界』に強いこだわりがある子が、豊かに生きていけるために私たち大人ができるサポートについて、徹底的にご紹介していきたいと思います!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
3~12歳【永久負け保存版】 子どもが勝ちや比較の世界で豊かに生きる育て方 9つの方法 /子育て勉強会TERUchより「勝ち負けへのこだわり」という才能をどう認識するか
 まずは大前提として、勝ち負けにこだわることは、どこまでいっても『長所』だと私は考えています。
まずは大前提として、勝ち負けにこだわることは、どこまでいっても『長所』だと私は考えています。
その子が生まれ持った気質の要素もありますし、自分を高めるための起爆剤となり、成長させてくれる頼もしい味方になってくれます。
「こだわりが強すぎて生きづらくなるのでは?」と心配されるかも知れませんが、それはどんな性格でも同じです。「優しい」性格だって、他人に譲りすぎて辛い思いをすることはあります。
勝ちに負けてこだわることも、こだわらないことも、どちらも良い面と悪い面があり、「どちらが良い・悪いという話ではない」と私は思います。
大切なのは、そのこだわりを「矯正する」のではなく「大切に活かす」という考え方です。
今、勝ち負けのある習い事などに熱中しているのであれば、それを辞めさせるのは本当にもったいないことです。
その熱中の体験を応援しつつ、
- 勝ち負けではない世界も体験させてあげる
- 勝ち負け以外の価値観を感じる声かけや関わり方をしてあげる
この子供らしいサポート、勝ち負けや白黒の価値観だけに縛られないバランスを取っていくのがベストだと僕は思います。
親ができる9つのサポート①基本スタンス

では、具体的にどんなサポートができるか、9つの方法をご紹介します!
以上が基本的な関わり方です。
- 悔しがっている時は共感し、少しでも感情を抑えられるサポートを
- 大人が負けた時を見本として「負けちゃったけど楽しかった!」などと意識して伝える
- 結果ではなく、過程(子どもの戦略やそこまでの態度)などに重点を置いて声をかけて
- 「1番を目指してね!」など、勝ち負けへのプレッシャーがかかる声かけはなかなかしない
テレビ視聴中に「勝たねえと意味ねえんだよ!」とボヤくのも、子どもは「勝たないと価値がないんだ」と学んでしまう可能性があるので、点検が必要かもしれませんね。
サポート②:他者比較をしない短い環境を作る
 皆さんの他の比較の傾向が強すぎるなら、少し環境を調整して、「自分の成長」や「探究」に重点を置いて時間を作って上げてみましょう。
皆さんの他の比較の傾向が強すぎるなら、少し環境を調整して、「自分の成長」や「探究」に重点を置いて時間を作って上げてみましょう。
1) 習い事環境などを見直してみる
勝ち負けのある習い事に熱中しているなら、それは大事にしつつ、別で一人で黙々と行う環境(造形教室やプログラミングなど)や、みんなで協力するような習い事を検討してみるのも良いバランスです。
2) 外で自由な遊び環境をもっと見てみる
習い事は、構造的に負けや比較(上手い/遅い、早い/遅い)をしやすい環境です。
目的のない「自由遊び」は、勝ち負けを意識せず、小さなトライ&エラーを繰り返しやすい貴重な時間です。 自然の中でワクワクする発見をしたり、遊具で遊んだりする体験の中で、負けない世界線の良さを感じさせてあげることができます。
サポート③:トライ&エラーが高速で遊べる遊びを増やす
 勝ちに負けにこだわる子が、緻密なボードゲームなどでも、毎回癇窹を引き受けて親も大変ですよね。
勝ちに負けにこだわる子が、緻密なボードゲームなどでも、毎回癇窹を引き受けて親も大変ですよね。
そんな時は、『努力したものの性質上、勝ち負けや成功失敗があっても気にしている暇がない遊び』がオススメです。
例「ジャンケンホイホイ」は、覚悟を決めて負けがありますが、スピード感があり、負けても気にする間もなく次が始まります。
このような子供らしい遊び、負けへの耐性をスモールステップでつけていくのも大事だと思います。
サポート④:ある程度子どもを見ていない時間を作る
 「子どもが勝ち負けや成功失敗にこだわるときはいつか?」と考えると、実は多くの場合、誰かが見ている時だったりします。
「子どもが勝ち負けや成功失敗にこだわるときはいつか?」と考えると、実は多くの場合、誰かが見ている時だったりします。
「恥ずかしい」「良いところを見せたい」「褒めてもらいたい」といった感情が、プレッシャーになるのです。
誰も見ていないので、周りを気にせずに自分の考えた解決ができます。 もちろん、子どもは「できたら見てほしい」生き物なのでバランスは必要ですが、もし親が見張りすぎても、と感じたら、適度に見ない時間を作るのも有効なサポートです。
サポート⑤:本や絵本で「白黒ではない世界」を教える
 親の言葉は黒くて素直に受け入れられなくても、本や絵本から「なるほどなぁ」と受け止められる価値観もあります。負けや白の世界ではない価値観を育むために読んでほしい4冊をご紹介します。
親の言葉は黒くて素直に受け入れられなくても、本や絵本から「なるほどなぁ」と受け止められる価値観もあります。負けや白の世界ではない価値観を育むために読んでほしい4冊をご紹介します。
-
1) 大ピンチずかん
日常のピンチを興味深く教えてくれます。失敗を恐れている子が、失敗を注意深く捉えるきっかけになるかもしれません。 -
2) しっぱいなんかこわくない!
夢のために挑戦し、失敗する女の子におばさんがかけた言葉が刺さります。勝ち負けとは違う、「挑戦」の価値を教えてくれる一冊です。 -
3) ま、いっか!
完璧主義者のお子さんや、親御さん自身が「ま! いっか!」と気楽に切ることを教えてくれる、肩の力がしっかり抜ける一冊です。 -
4) かまわなくても大丈夫 (ガストンのソーシャルスキルえほん)うまくいかなくてもすねない
、あきらめない、やり直すことで上達することを優しく教えてくれる絵本です。
サポート⑥:他者比較から「自分がやるべきこと」へ思考を転換する
 これは私が個人的に最も大事にしている考え方です。
これは私が個人的に最も大事にしている考え方です。
よく「他人と比べな、過去の自分と比べろ」と言われますが、他人比較をしてしまう自分を無理に変える必要はないと思います。
私も YouTube の数字を周りと比べて一喜一憂しています。しかし、その比較している時間は何もありません。
大切なのは、『他人比較をしてしまう自分は認めつつ、一瞬も早く「じゃあ自分にできることは何だ?」と次の行動を意識してみる』ことです。
この思考回路を子どもにも育てたいのです。
具体的には、子どもが負けて癇窹を起こしている時、
「そんなことはないの!」
などと言わず、まずは「ちょっと悔しかったね。その悔しさは〇〇くんのすごいパワーだね」と感情を認めます。
そして落ち着いたら、「今よりもっと上達するためにできることはあるかな?」と問いかけます。
「自分ができること」を意識する練習になることが重要なのです。
サポート⑦:誰かと「協力する」や遊び体験をする
 勝ち負けの対極にあるのは『協力』です。
勝ち負けの対極にあるのは『協力』です。
もし極度に勝ち負けにこだわるなら、意識して「協力して何かを大事に」経験をさせてあげることで、負け勝ちではない世界の良さを感じてくれるかもしれない。
例「みんなで協力して全てのお題をクリアするジェスチャーゲーム」など、勝ち負けせずに、お互いに協力しながらクリアを目指して遊びを取り入れてみるのも良いですね。
サポート⑧:勝負事の前に負けの考え方を教えてから始める
 多くは負けた「後」の対応に関心がありますが、実は『勝負事の始め方』も大切です。
多くは負けた「後」の対応に関心がありますが、実は『勝負事の始め方』も大切です。
勝負事を始める前に、子どもと「勝っても威張らないこと、負けても怒らないこと」というルールを確認し、その理由(威張ったら相手が嫌な気持ちになる、など)も伝えます。
とりあえず、大人もそのルールを守り、「楽しかったね!」「今の戦略先生たね!」と、結果ではなくプロセスや楽しさ自体に重点を置いた言葉をかけてほしいです。
サポート⑨:泣くこと・悔しがることを「練習」と悔しさ
 負けた時や失敗した時の癇癪は、本当に大変だと思います。
負けた時や失敗した時の癇癪は、本当に大変だと思います。
しかし、私はその時間を『それを乗り越えようとする練習』と捉えています。
緩やかは、負けて癇窹を起こすことがダサイことなんてわかります。
その状態から立ち直るには「練習」しかありません。
したがって、癇癪の時間は、子ども自身が折り合いをつけられない自分と戦っている「成長の時間」なんです。
その視点を持った上で、すぐに介入せず、あえてあげてあげる。 そして自分で立ち直った時、「よく乗り越えたね!」と認めてあげる。
【まとめ】「勝ち負け」のこだわりを、最強の武器に変える
今回は、勝ち負けにこだわる子へのサポートを9つご紹介しました。
- 基本スタンス:結果より過程を褒め、「勝たないと意味がない」という価値観を伝えない。
- 環境調整①(習い事): 勝ち負けのない習い事も経験させ、バランスを整える。
- 環境調整②(遊び):トライ&エラーを高速で考えられる(ジャンケンなど)を取り入れる遊び。
- 環境調整③(親の葛藤):親が「見ていない」時間をかけて作り、プレッシャーから解放する。
- 入力:絵本など、負けや白黒以外の価値観を感じさせます。
- 思考の転換:他者比較を認めた上で、「今度は自分にできることは?」と次の行動を考える練習をする。
- 協力体験:ジェスチャーゲームなど、勝ち負けのない「協力」遊びを取り入れます。
- 事前のルール化:「負けても怒らない」などのルールを対戦前に確認し、親も見本を見せる。
- 捉え方:癇癪の時間、子どもが自分と向き合う「成長のための練習」と反省。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
幼児教育講師TERUでした。