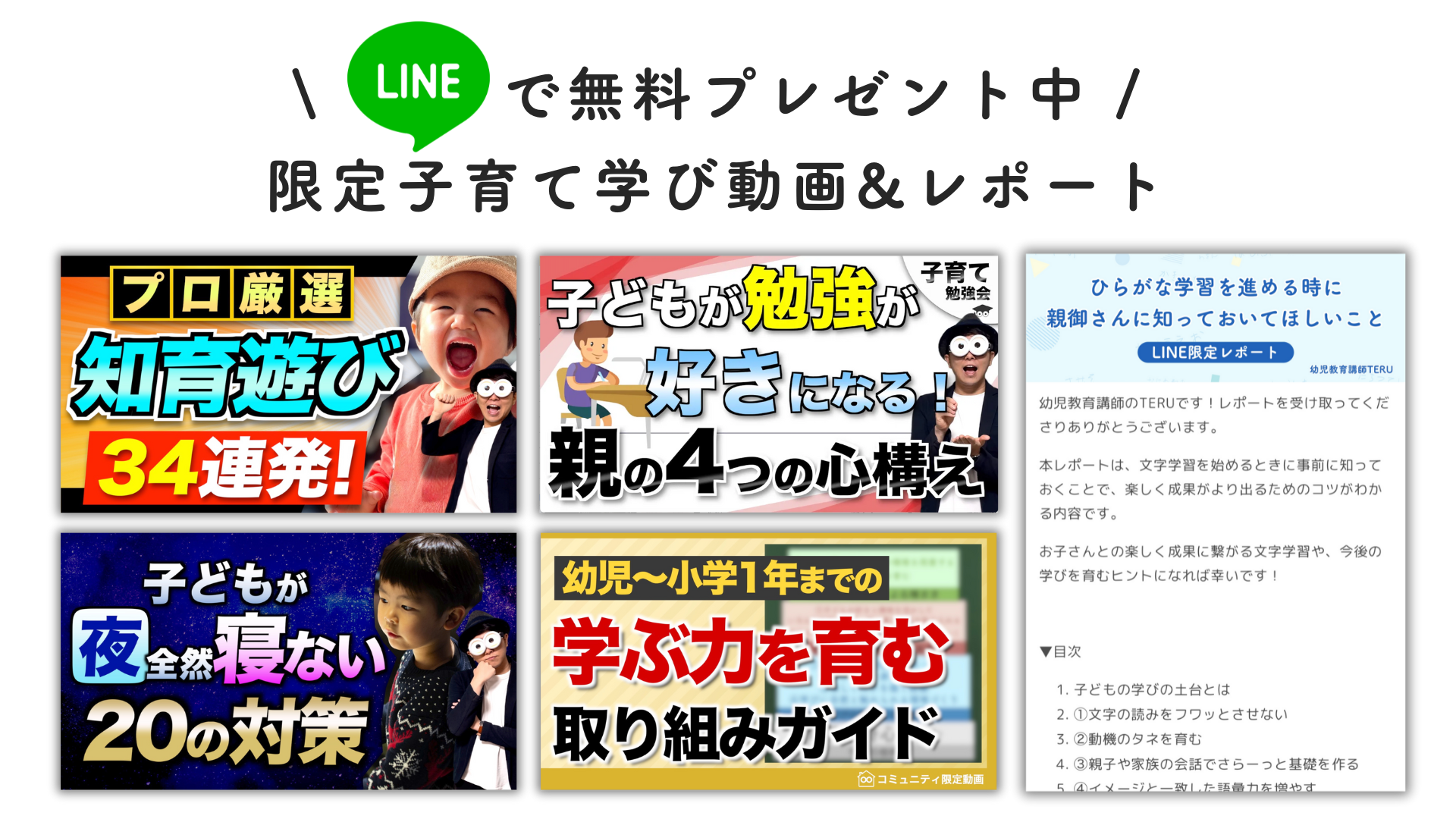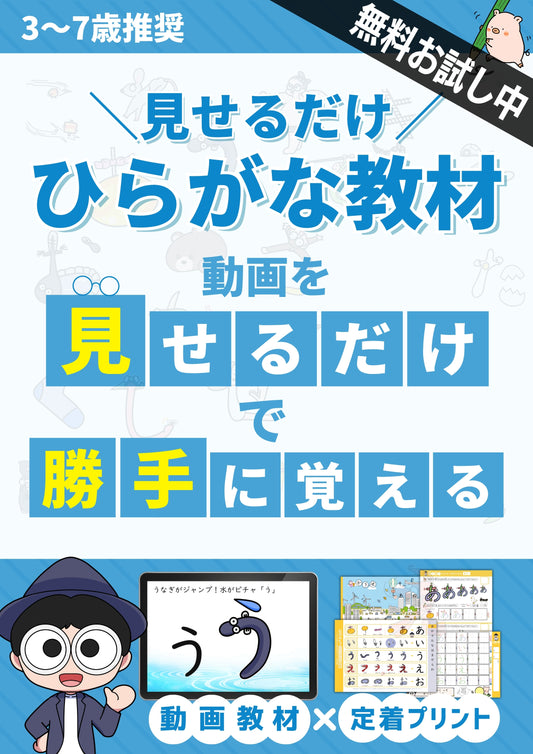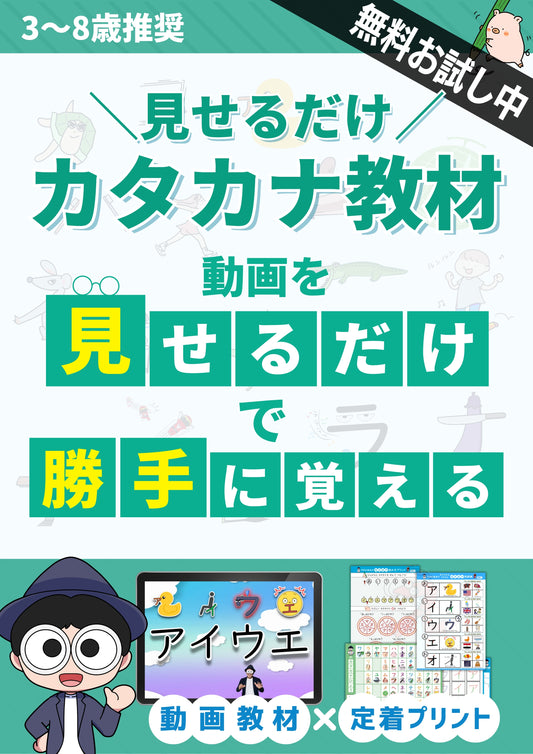「『地頭が良くなる』家庭環境みたいな動画を最近ですが、TERU先生はどんな環境がオススメですか?」
このようなご質問をいただきました!
段階の脳の視点から、幼児教育者として伝えられることをご紹介してみたいと思います
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
2~12歳【脳科学】①子どもの地頭を良くする家庭環境②勉強や習い事の継続ができない時の親の関わり方子育て勉強会TERUchより【目次】
- 地頭の要素とは?
- 「メタ認知」とは?その働きは?
- メタ認知を育む家庭の環境づくり
- 【まとめ】「もう一人の自分」を育てる家庭の習慣
地頭の要素とは?
 まず前提の話ですが、地頭って一応概念的なんですよね。 地頭が良いって本当に色々な口から語れます。
まず前提の話ですが、地頭って一応概念的なんですよね。 地頭が良いって本当に色々な口から語れます。
例、
- 脳のスペックと呼ばれるワーキングメモリ
- の思考や行動をコントロールする「機能」(メモリーも実行機能と深く重要な要素の一つ)
- 知的好奇心などの非認知能力
- メタ認知能力
これら全て、地頭が良いという概念に注目されるんですよね。
それが先の上で、今日は『メタ認知能力』に絞って、それを育む家庭環境について話していきたいと思います!
さて、ワーキングメモリについては過去にもいろいろな動画で話をしていて、例えばこちらの
の動画を見てください、ご家庭で育むポイントをご理解いただけると思いますので、ぜひご覧くださいね!
あ、僕が運営する「TERU先生の動画教室」でも、僕が作った子ども向け教育動画を使うだけでメモリーを育むコンテンツをたくさん配信していますので、なかなか皆さんの地頭を育んであげたいという方は、使ってみてくださいね!
「メタ認知」とは?その働きは?
 では、まず「メタ認知」ってそもそも何?ってことなのですが、この理解はかなり大事なので丁寧に説明しますね!
では、まず「メタ認知」ってそもそも何?ってことなのですが、この理解はかなり大事なので丁寧に説明しますね!
メタ認知を一言でいうと、
「もう一人の自分が、自分自身を客観的に見ている状態」のことです。
メタ=「迷宮の」「超越した」という意味のギリシャ語が語源
認知=「知る」「考える」「珍しい」といった頭の働きのこと
そこで、そこは、自分の「認知」を一歩高い視点から観察・制御する能力を目指すためにです。
メタ認知には2つの働きがあって、
-
モニタリング機能
「うーん、このやり方だと時間がかかりそうだな」「あ、集中力が切れてきたな」と、自分の状態や考え方を客観的に把握する機能。 -
コントロール機能:
「よし、やり方を変えてみよう」「少し休憩して集中力を回復させよう」と、モニタリングした結果をもとに、自分の行動を修正・調整する機能。
これらの機能が高いとどうなるのか?
- 合った勉強法を見つけたり、間違いにすぐ気づいて修正したりできることにより、学習効率が上がります
- 行き詰まった時に、冷静に状況を分析して、別の解決策を試せるので、問題解決能力が高まる
- 「あ、今自分イライラしてるな。深呼吸しよう」と、感情に飲み込まれてしまうので、感情をコントロールしやすくなる
結論、こういう人は地頭が良い人だよね。
メタ認知を育む家庭の環境づくり
 ということで、ここまで概念の説明をしてきましたが、ここから具体的な環境づくりをご紹介しますね!
ということで、ここまで概念の説明をしてきましたが、ここから具体的な環境づくりをご紹介しますね!
メタ認知を育む方法は色々あるのですが、紹介しすぎても情報過多なので、3つオススメを紹介します!
①親が時折ひとりごとを言う
 失敗は、親の思考プロセスを真似することで、自分の思考を客観視する方法を学んだりします。
失敗は、親の思考プロセスを真似することで、自分の思考を客観視する方法を学んだりします。
例、料理をしながら
「まず野菜を先に、次にお肉を焼いて…あ、フライパンを先に温めないとダメか」
と、考えていることをそのまま口に出してみられる感じですね!
個人的には失敗したときや、困難にぶつかったときこそ、ひとりごとで思考プロセスを公開して欲しいなと思いました!
例、
「今日の仕事上手くいかなかったなぁ、でもうまくいかない原因を見つけて、何度も挑戦すればちゃんと成功できるようになるから諦めないで頑張ろう」
とか、そのようなことをひとりごととして呟きながら、子どもに聞かせてあげることで、
メタ認知だけではなく、失敗しても立ち直る力であるレジリエンスにつながる良い考え方を言って言うことができますね!
②優れた理由をインタビューする
 なんだかうまくいった時、もちろん褒めたりするのもいいですが、どううまくいったのかをインタビューのようにあげて、メタを育む関わり方になります。
なんだかうまくいった時、もちろん褒めたりするのもいいですが、どううまくいったのかをインタビューのようにあげて、メタを育む関わり方になります。
例、子どもが粘土で作品を作ります。それを自慢して見せてくれました
「お!よく作ってるね!どうやって作ったの?どんなところを工夫したらこんな上手にできるの?」
などと、作る過程や、過程でのこだわりを説明して受け取るつもりです。
③作戦会議を意識的に取り入れる
 皆さんは皆さんと作戦会議ってしたの?
皆さんは皆さんと作戦会議ってしたの?
例、部屋をみんなで片付けます。
片付け始める前に
「このお部屋の片付け、どこからやったら一番早く終わりそう?」
「お母さんはどこを担当したら効率良いかな?」
と暫定ライトな計画を立てるように問いかけます。
そして片付け終わったら
「セーターの作戦やってみてどうだった?」
「次はどんな順番で片付けるともっと早く片付いたかな?」
こんな感じで立てた計画や作戦を振り返って、また問いかけます。
ガチっとした感じの会話じゃなくていいので、本当にさらっとライトに少しだけ皆さんに考えさせてください。これだけでも十分メタ認知を育む機会になります。
【まとめ】「もう一人の自分」を育てる家庭の習慣
- 「地頭」の鍵はメタ認知:「自分を客観視する力」が学習効率や問題解決能力の土台となる。
- 親の「ひとりごと」が最高の教材:親が思考のプロセスを口に出すことで、子どもは考え方を学ぶ。
- 「成功インタビュー」で振り返って:「どううまくいったの?」という質問が、自分の行動を客観視する練習になる。
- 「作戦会議」で計画と修正を経験する:事前の計画と事後の振り返りを習慣化することが、メタ認知を強力に育てる。
無理、以上、できる限りできる範囲で入ってくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
幼児教育講師TERUでした。