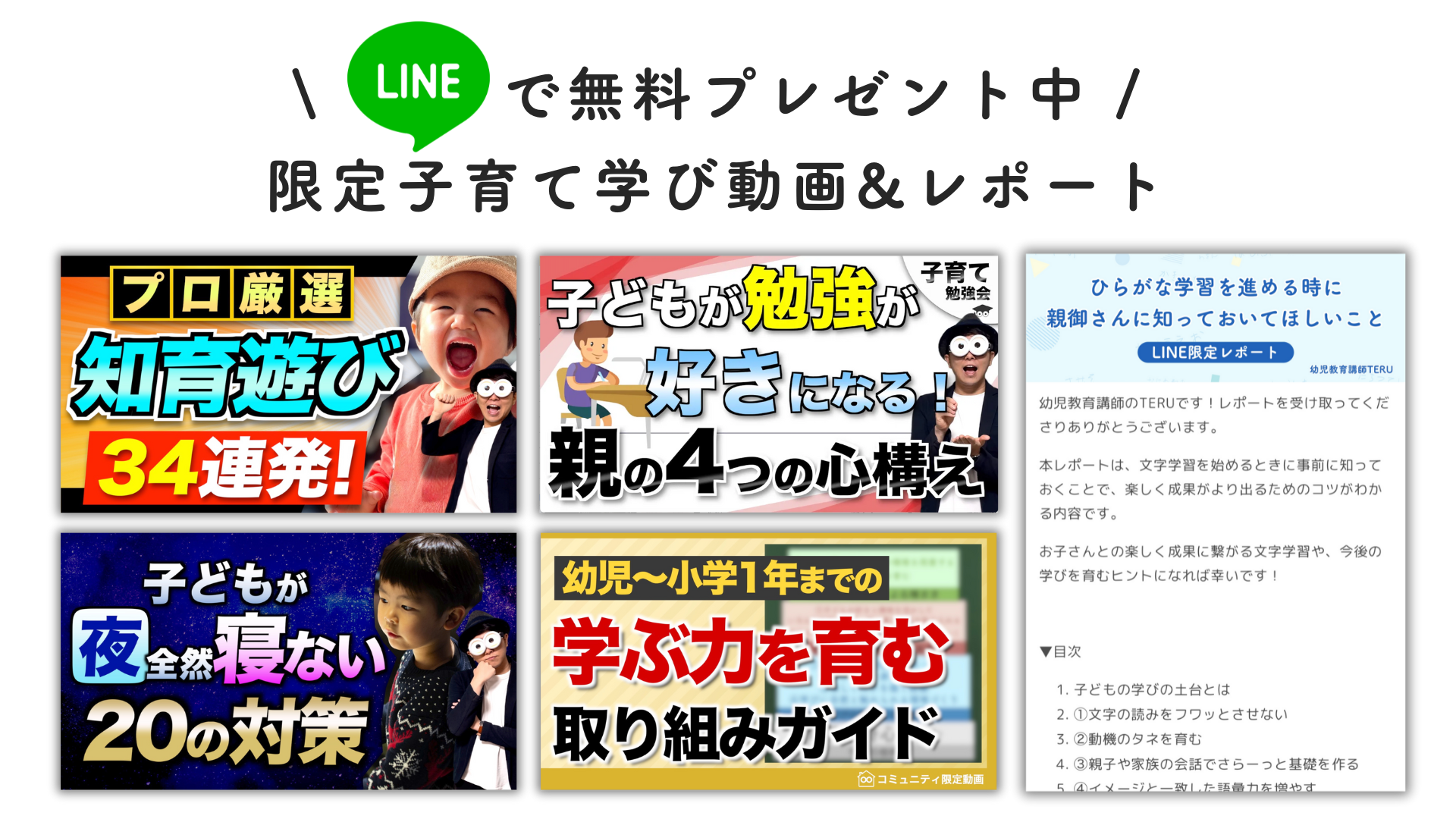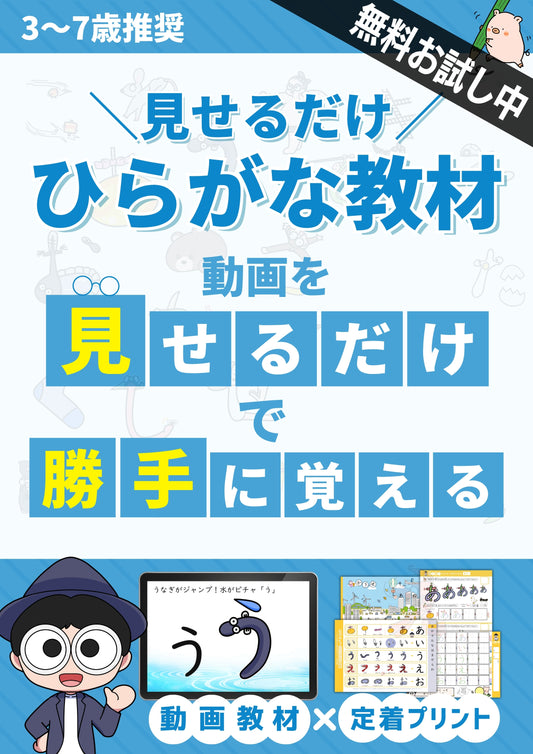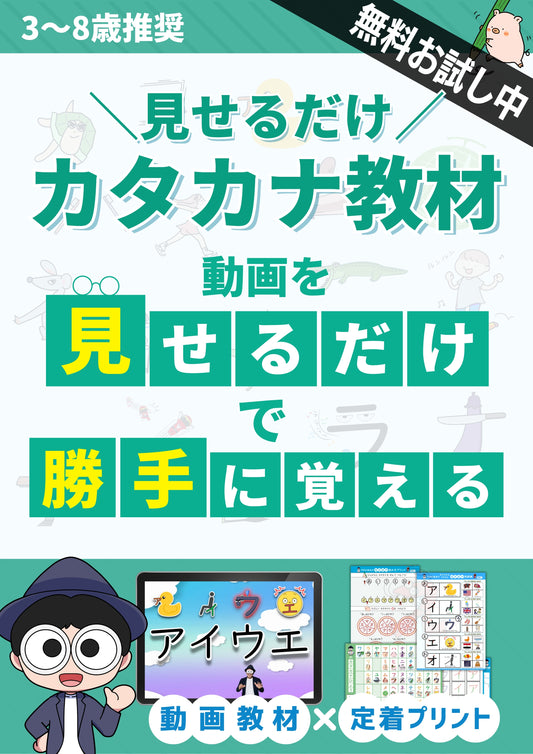「うちの子、全然言うことを聞かない。このままだと、どんなわがままな子に育ってしまうのだろう…」
そんな不安を和らげてくれるかもしれない、いくつかの研究をご紹介します。きっと皆さんが何となく感じていることかもしれませんが、「事実ベース」で理解しておくことは、子育てにおいて非常に大切だと思ったのでシェアしますね。
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
【たった1つ】男の子の子育てで気をつけたい親のNG行動 / 子育て勉強会TERUchより【目次】
- 「聞き分けがない子」の驚くべき将来
- 協調性が高すぎる男性は年収が低い?
- なぜ男女差があるのか?
- 現実的な「ルール教育」の3ステップ
- 【まとめ】不安な気持ちとの付き合い方
「聞き分けがない子」の驚くべき将来

ドイツの心理学者ヘッツァーが、ある有名な追跡調査があります。彼は、2歳から5歳の時期に強い反抗期を示した子どもたち100人が、青年期にどうなったかを調べました。
その結果、非常に興味深い事実が浮かび上がってきました。
それは、聞き分けのなかった子どものうち84%が、大人になったときに「意志が強く、しっかりとした判断力のある人間に育っていた」ということです。
「言うことを聞かない」というのは、裏を返せば「自分の意志を持っている」ということ。今は困った姿に見えても、将来は大きな強みになる可能性があるのです。
とはいえ、そうは分かっていても、「もう少し言うことを聞いてほしい」というのが親御さんの本音だと思いますが、この研究結果は一つの勇気になりますよね。日々の子育て、本当にお疲れ様です。
協調性が高すぎる男性は年収が低い?

これに関連して、もう一つ面白い研究があります。コーネル大学のリビングストン博士らの調査によると、「協調性が高すぎる男性は、年収が低い傾向がある」という結果が出ています。
この研究では、約9000人を対象に性格診断テストを行い、協調性と年収の関係を分析しました。
その結果、協調性が高い男性は、低い男性に比べて平均で約80万円ほど年収が低い傾向が見られたそうです。
ちなみに女性の場合、その差は平均約12万円ほどで、大きな違いは見られませんでした。
なぜ男女差があるのか?

この男女差について、研究では「人の進化における役割分担」が関係していると考察されています。
男性は古来、狩りをして生き抜いてきました。獲物を手に入れるには、ルールに忠実であること以上に、瞬時の判断力や、常識にとらわれない柔軟な発想力が求められた、ということのようです。
現実的な「ルール教育」の3ステップ

ここまで「言うことを聞かないのも良い面がある」というお話をしてきましたが、もちろんそのまま放置して良いわけではありません。社会のルールやマナーを守れないと、本人が辛い思いをすることもあります。
そこで、子どもがルールを身につけるための「3つの段階」をご紹介します。
- ルールを「知る」
- 大人のサポートのもと「守れて嬉しい」を経験する
- 自分でできるようになる
■1段階目
まず1段階目は、親がルールとその理由をセットで伝えます。
「公共の場では騒いではいけないよ。他の人に迷惑がかかるからね」
「遊具は順番を守ろうね。割り込まれたら悲しい気持ちになるよね」
というように、具体的に教えます。
場合によっては、高濱先生の「おやくそく」絵本のようなものを使うのも非常に効果的です。
■2段階目
次に、意外と抜けがちなのが2段階目です。ルールを教えたら終わりではなく、実際に親が一緒に順番に並び、待てたことを「ちゃんと順番に並べたね!お兄さんみたい!」「周りのことを考えられる力があるね!」と具体的にフィードバックしてあげます。
ルールを守れたことが「嬉しい経験」となり、「自分はルールを守れるんだ」という自信につながります。
■3段階目
そして3段階目が「自分でできるようになる」です。もし、1・2段階を丁寧に繰り返しても、なかなか3段階目にいけない場合。僕個人の考えですが、それはある程度「仕方がない」ことだと思っています。
もちろん、命の危険などに関わることは別ですが、それ以上叱り続けても逆効果になることもあります。親ができることをやったのなら、あとはお子さん自身が「守る必要がある」と気づく体験を待つ、という「良い意味での割り切り」も大切ですね。
これが難しいんですけどね。。
ちなみに、叱りすぎる逆効果については以下の動画『【今日からできる】子育てが変わる簡単な方法』で話しているので、そちらも良かったらご覧ください。
【まとめ】不安な気持ちとの付き合い方
今回は、「言うことを聞かない子」に対する新しい視点をお伝えしました。
- 反抗的な子は、将来「意志の強い人」になる可能性がある。
- ルールは「知る→嬉しい経験→自立」の3段階で丁寧に教える。
- 親ができることをやったら、あとは「割り切り」も大事。
子育ての不安は尽きませんが、科学的な事実を知ることで、少しだけ肩の力を抜けるかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。