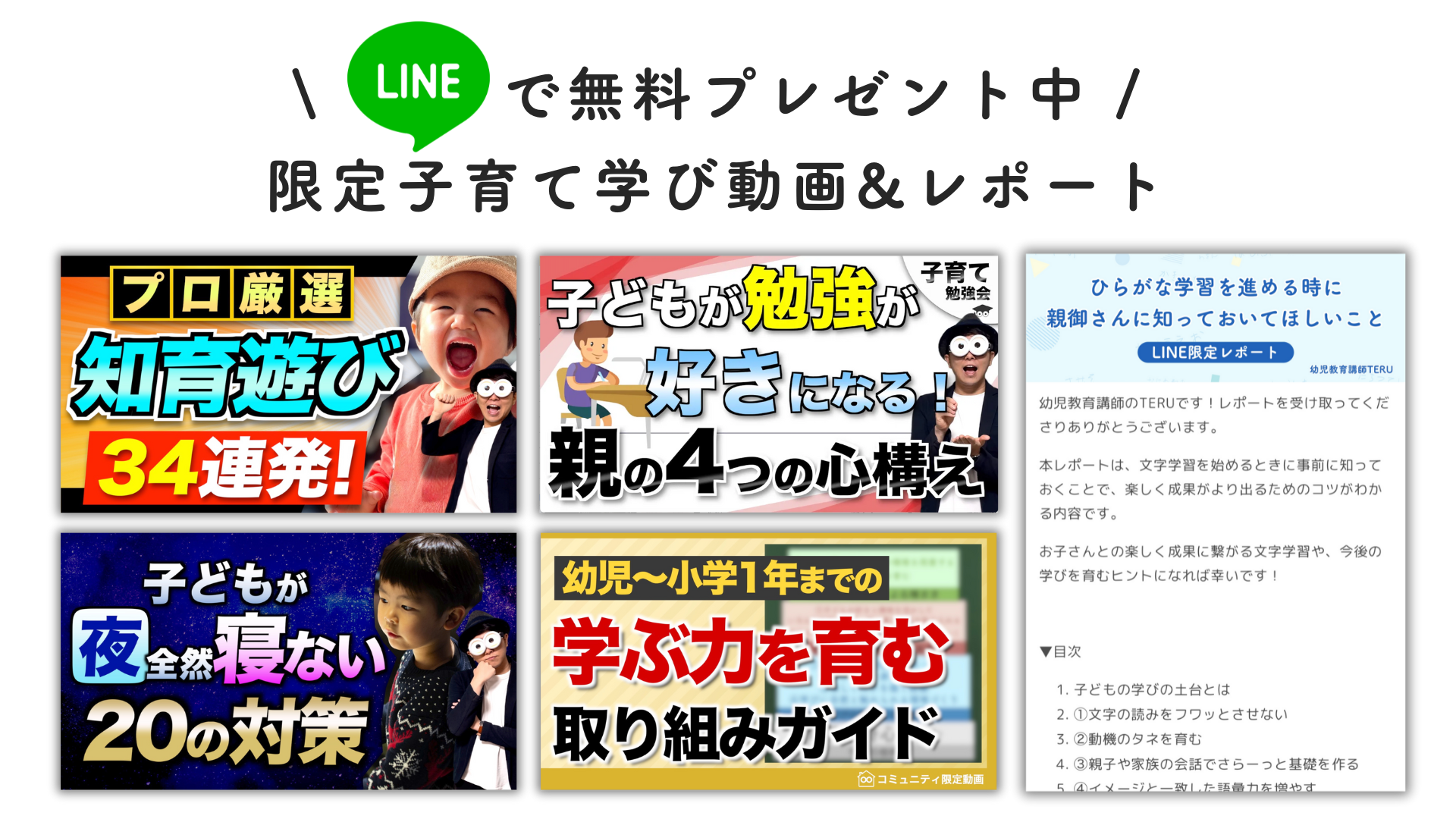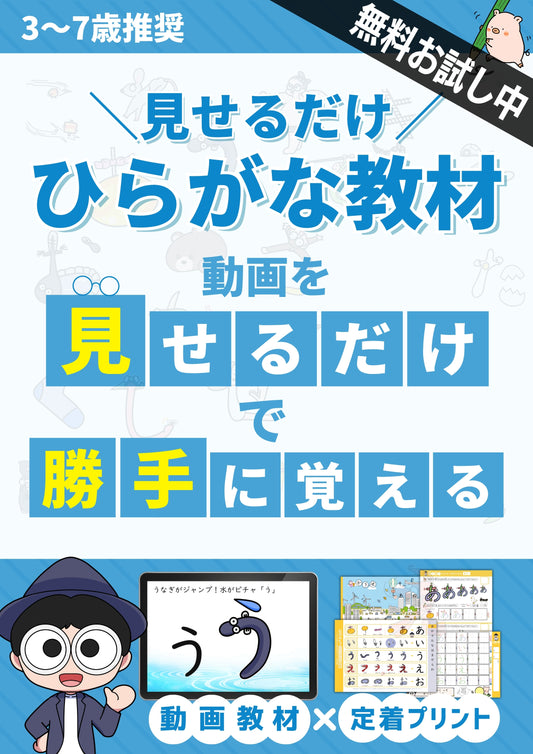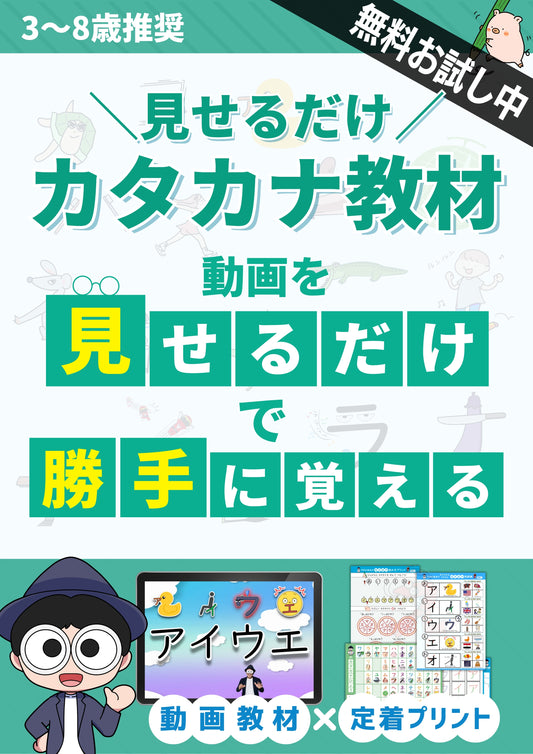「子どもがイオンやスーパーで毎回走りにいきます。何か親ができることはありますでしょうか?」
ようなご質問をいただきました!
何か1つでもヒントがあるように、できることを色々挙げてみます!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
スーパーやショッピングセンターで走り回る子にどう対応するのがベスト?子育て勉強会TERUchより事前にミッションを決めておく
 目的意識を持つと、脳の前頭前野が活性化して衝動的な行動を抑制しやすくなると言われますね!
目的意識を持つと、脳の前頭前野が活性化して衝動的な行動を抑制しやすくなると言われますね!
例1:食材探し担当
定番ですが、「〇〇君は、これとこれの食材を探す役割をやってくれる?」という役割を与えてあげるのも効果的ですね!
例2:エコバックを渡す
小さなエコバッグを渡し、「これはあなたのバッグ。ここにパンと牛乳を入れるの仕事がおだよ」と任せる。自分のすべての物があることで、より責任感が芽生えますね
例3:カートを押す担当
これはよく行われていると思いますが、素晴らしい役割の1つですね!楽しくなってカートで暴走してしまう場合もありますけどね😅笑
例4: 通信担当
5歳くらいはまだ時間の予定を立てるのが苦手で、「あとどれくらいで終わるか分からない」という不安が、落ち着きのなさに繋がることもあります。
ポイント
されている方も多いと思いますが、いくつかの役割の選択肢から、お客様に選んでもらうと自己決定感からより役割に意識が向きやすくなりますね
身体の状態を整えておく
 1)行く前に、身体を確保する
1)行く前に、身体を確保する
エネルギーが残っている時に、スーパーという閉鎖空間でそれを考えるのは難しいですよね。
2) 無意識・疲労状態を気にする
逆に、知覚や疲労困憊の状態で血糖値が下がると、脳の自己制御機能が低下します。 おにぎりなどを少し食べてから行く、お昼寝の後に行くなどすると「走ってはいけない」というルールへの自己抑制が発揮しやすい状態になりますね!
代替案を渡しておく
 例
例
「走りたくなったら、その場でジャンプを3回転してみようか!」
などなど、衝動を別の安全な行動に留めておきます。
代替案は他にも色々あると思いますが、何かフィットするものがあれば、走りたい欲求を別の行動で満たせるかもしれませんね!
線の上やこの色のタイルだけを歩くゲーム
 スーパーの床のタイルやタイルとタイルの間の線などを使って「線の上からはみ出さないように歩けるかな?」と遊びを提案すると、みんなが頑張ってくれたら衝動的に走り出すのを抑制できることがありますね!
スーパーの床のタイルやタイルとタイルの間の線などを使って「線の上からはみ出さないように歩けるかな?」と遊びを提案すると、みんなが頑張ってくれたら衝動的に走り出すのを抑制できることがありますね!
線の上を歩くというミッションに意識が向くのもありますが、さらに体のバランス感覚(前感覚庭)と、自分の体の位置を把握する感覚(固有感覚)を同時に使います、脳への適度な刺激になって、走り回るという大きな動きの欲求をしやすくしてくれます!
探偵ゲーム
 「赤い野菜はどこかな?」「『と』がつく何かを探そう!」など、視覚探索のゲームをすると、走り回るという衝動的な行動に注意が向いたりしますよね!
「赤い野菜はどこかな?」「『と』がつく何かを探そう!」など、視覚探索のゲームをすると、走り回るという衝動的な行動に注意が向いたりしますよね!
感覚に過敏な場合はイヤーマフを挑戦する
 スーパーの騒音、館内放送、人のざわめきなどが苦手で、その不快感から走り出してしまうこともあります。
スーパーの騒音、館内放送、人のざわめきなどが苦手で、その不快感から走り出してしまうこともあります。
走った時ではなく、走っていない時に反応する
 私たちはどうしても、皆さんが良くない行動をしたときに注意するなどの反応をしてしまうことが多いのですが、それがドーパミンのトリガーになってしまうことが起こります。
私たちはどうしても、皆さんが良くない行動をしたときに注意するなどの反応をしてしまうことが多いのですが、それがドーパミンのトリガーになってしまうことが起こります。
そうならないために、歩いて行動できるときに「
一緒に歩いてくれてお母さん助かるよ!」 「
今日は走らないで歩いているね!お兄さんみたいだね!」 など、
時々ちゃんと声を出しているのも大事ですね!
大人が意識を注目する行動を強化しようのが、子どもの行動原理の1つです
&ストップゴー課題
 これは、その場での対応ではなく、本質的に子どもが自己抑制ができるよう力を育む方法ですね。
これは、その場での対応ではなく、本質的に子どもが自己抑制ができるよう力を育む方法ですね。
ストップ&ゴー課題は、脳の機能の中の抑制制御と呼ばれる実行能力を鍛えるトレーニングです。
▼&ストップゴー課題の代表的な遊び
- だるまさんがころんだ
- い取りゲーム
- ジェスチャーゲーム
- フリーズダンス(音楽をかけている間は自由に踊り、音楽が止まった瞬間に氷のように固まる遊び)
あ、シンプルなストップ&ゴー課題ではありませんが、以下もオススメです!
- あべこべゲーム(親が言ったことと反対の行動や言葉を子どもにやってもらう遊び)
頭で考えたこと(立つ)をそのまま実行する、という自動的な反応を意識的に止める(抑制し)、さらに「反対は何か」と考え(メモリーワーキング)、正しい行動に努めるという、非常に高い前頭前野のトレーニングです!
【まとめ】多角的なアプローチで対応しよう
今回は、スーパーなどで子どもが走り回ってしまった時の対策8つご紹介しました。
- 事前準備:ミッションを与えたり、身体の状態を整えてから行きます。
- その場での工夫:代替案を渡したり、床の線や商品でゲームをする。
- 感覚への配慮:騒音が苦手な子にはイヤーマフを挑戦します。
- 関わり方の工夫:走っていない時にこそ注目し、肯定的な声をかける。
- 長期的なトレーニング:「だるまがころんだ」など、自己抑制を育む遊びを日常に取り入れる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
幼児教育講師TERUでした。