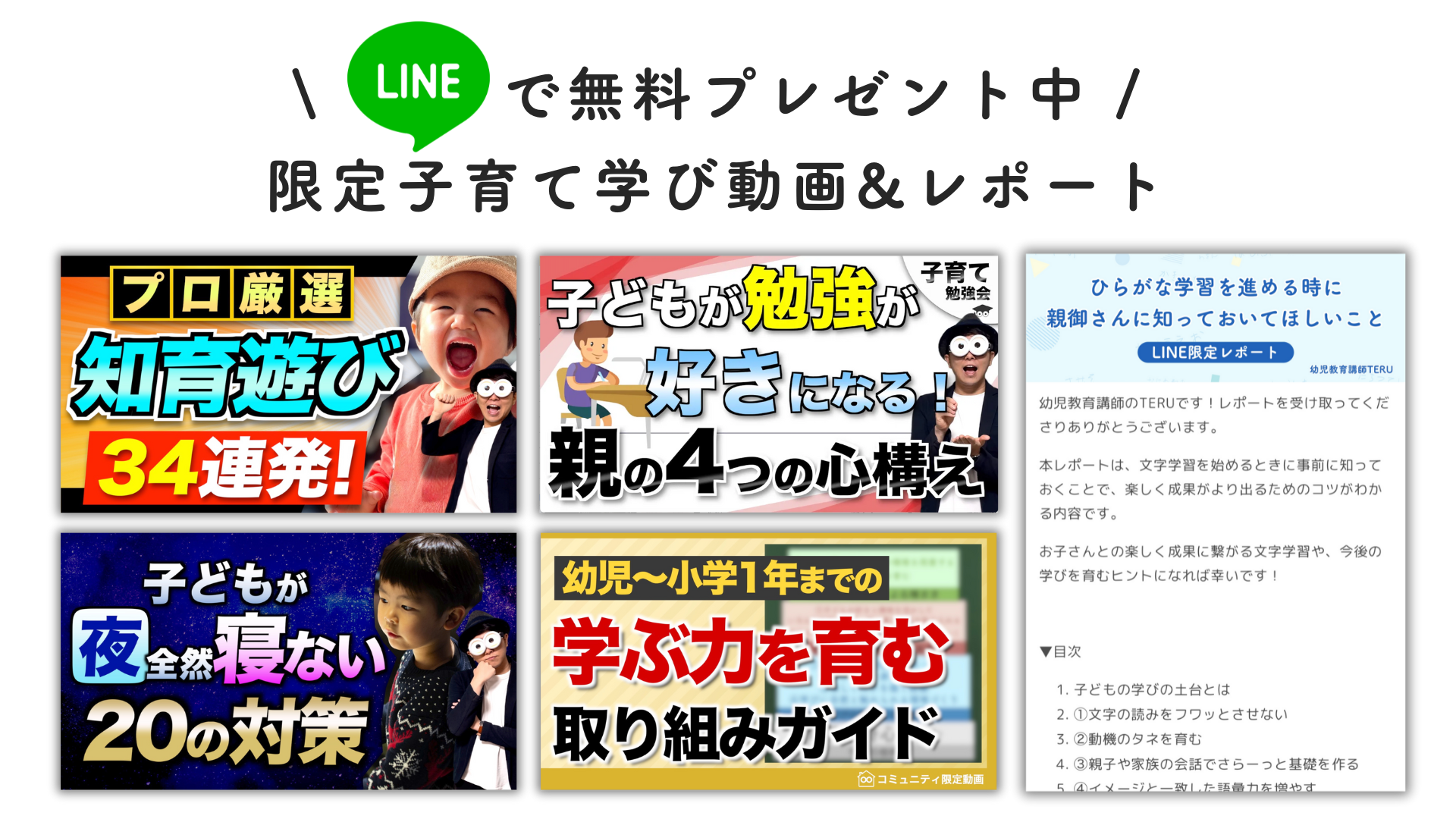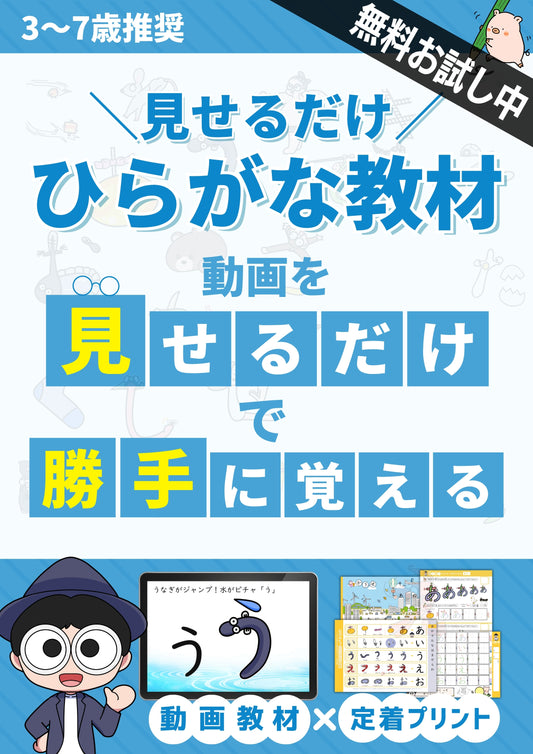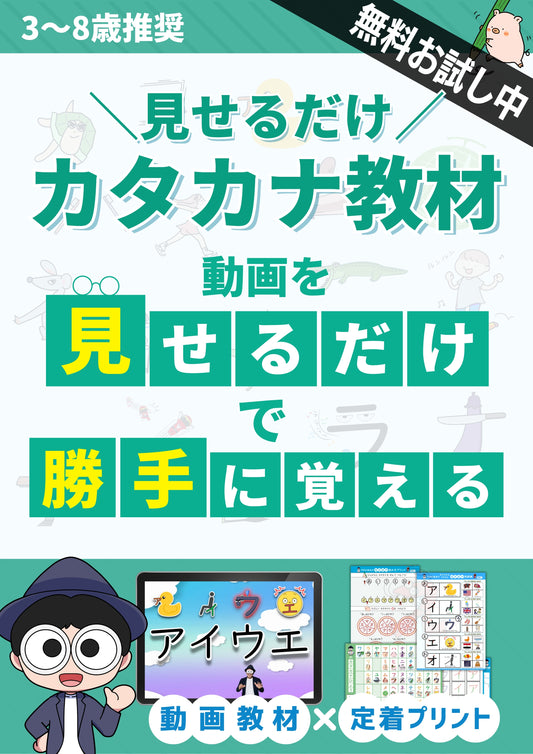今日のテーマは『子どもをダメにする親が知らない残酷な真実』
ちょっと怖いタイトルになってしまいました。
私は、これまで多くの子どもたちのサポートをさせてもらって、さらに子どもの脳や心のことについて様々学ばせてもらってきました。
そう子どもについて学んでいると、必ず出会う子どもの脳のある仕組みがあります。
今日はそれについてお話しさせていただき、できる限りできる範囲で、子どものより良い成長をサポートできる私たちでいれるヒントになれば幸いだと思います。
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
0~12歳【幼児教育講師が語る】子どもをダメにする大人が知らない真実 /子育て勉強会TERUchより【目次】
- 残酷な真実:脳はネガティブが大得意
- 安易なダメ出しが可能性を狭める理由
- ワーク①:決めつけで会話しないの?
- ワーク②:過去のことだけ口にしていないか?
- ワーク③:自分の「正しい論」と向き合う
- 【まとめ】完璧でなくていい。意識することが大事
残酷な真実:脳はネガティブが大得意
 では早速結論ですが、僕がいつも頭が真っ白だなぁって思う 子どもの脳の癖は『子どもの脳は偏見に強い』だということです。
では早速結論ですが、僕がいつも頭が真っ白だなぁって思う 子どもの脳の癖は『子どもの脳は偏見に強い』だということです。
これは子どもだけの話ではなく大人も同様ですし、その度合いの個人差は当然あります。
否定って具体的などんな感じかと説明すると、次の4つの通りです。
- 人の脳はネガティブで注目しやすい
- 人の脳はポジティブなことよりもネガティブなことを強く記憶する
- 人の脳は決断をする一度過去の情報を引き出しながら総合的に判断する
- 人の脳は記憶を思い出すときネガティブな記憶を強く思い出してしまう
これが人の脳の癖です。
安易なダメ出しが可能性を狭める理由
 それは『安易なダメ出しが子どもの可能性を狭めてしまう』ということです。
それは『安易なダメ出しが子どもの可能性を狭めてしまう』ということです。
その時の4つを元に、子どもにネガティブなダメ出しをしたら考えると
- そのダメ出しに強く注目し
- その被害が出たことを強く記憶して
- 何か次の挑戦や決断をする際に
- そのダメ出しを強くして思い出してしまう
こんなことが子どもの頭の中ではあります。これがどういうことか?お分かりいただけると思いますが
『ダメ出しをすればするほど、子どもはポジティブな挑戦や決断がしづらくなってしまう』ということです。
すみませんまた怖いことを言ってます。でもこれは今大人は知らないといけないことだと思います。
必要な指摘はありますし、必要な叱責行為もあります。
ここから、ダメージ出しを減らすための3つの仕事をやってみよう!ワークとは、3つの簡単な問いについて考えてみるだけです。
ワーク①:決めつけで会話しないの?
 不幸へのネガティブなダメ出しがもっと原因の1つとして『つけ決め』があると思っています。
不幸へのネガティブなダメ出しがもっと原因の1つとして『つけ決め』があると思っています。
ダメ出しは子どもの良くない発言や行動に対してよくあるものですが、実はそのように見えて良くない発言や行動の裏にある『子どもが考えていたことや事情』には一応、自分のイメージで決めつけてしまうことが故に、悪くても良いダメ出しをしていることも多いです。
「そんなところに書いちゃダメでしょ!」と叱りたくなりますが、話を聞いてみると「ママが前に絵を描いたら喜んでくれて、また楽しくしようと思って…」という想いが見えてくるかもしれません。
だったら、「その気持ちは嬉しいよ。でも壁だと消えないから次は紙に描いてね」という言葉がけに変わるかも知れませんよね。
日々表面的に見える子どもの発言や行動を「決めつけ」で決めず、まず聞いてコミュニケーションを取ったり、あったのかな?
ワーク②:過去のことだけ口にしていないか?
 2つ目の問いはこれです。
2つ目の問いはこれです。
「ダメ出しをしない」みたいな話だと、怒らず怒らない立場に偏っているのですが、それはそれで子どもに良くない影響になってしまうことが多いです。
大事なことを指摘する場面でも『過去ではなく未来に向けた言葉を心がける』ことだと思います。
例、水をこぼしたシーンで
「またこぼしたの?昨日も同じことしたよね」
これは全部過去のことに対しての言葉ですよね。
そう言いたくなる気持ちは本当に分かりますが、頑張って未来に向けて
「次はどうすればこぼさないで運べるかな?」
こんな感じの言葉でコミュニケーションが取れて良いですね!
そう未来に向けた言葉を心がけると、自然とダメ出しが増えていくのと、さらに子ども自身に向けてダメ出しをされていると感じることが少なくなっていたりします。
ただ、1点気をつけて欲しいのが、未来に向けた言葉でも『問い詰め』にはならないように気をつけてください。
「あと何回言えばわかるの!?」なんて言葉は、未来の話を聞いているようですが、ただ問い詰めです。
ワーク③:自分の「正しい論」と向き合う
 3つ目はこれです。 正しい論とは要するに「こうあるべき」という自分の中の考えのことを言うわけですが、この正しい論があると残念ながらダメ出しが多々あります。
3つ目はこれです。 正しい論とは要するに「こうあるべき」という自分の中の考えのことを言うわけですが、この正しい論があると残念ながらダメ出しが多々あります。
人は、こうすべきという考えがあると、じゃない状況や意見があるのを見たときにモヤモヤしてしまうものです。
ただし、少しだけでも「正しい論」を手放していることとして、今までよりダメ出しをしてしまうことが減っていきます!
私なりの方法を3ステップでご紹介させていただきますね!
ステップ①:自分の中の大切な論の棚卸しをする
「なんとなく欲しい」「こうなって欲しい」「
拘らずに良いのにこだわってしまう」など、思いつくままに書いてみましょう!
こうやってまず自分の正しい論を俯瞰してみてみるときっと気づいているものがあって、子どもとの関わりや自分の在り方の生き道が少しずつ見えてきた。
ステップ②:優先順位を決める
正しい論の棚卸しをしたら、その中から自分にとって優先順位が高いもの3つくらいに丸をつけてみてください。そして丸を付けたもの以外は「今こだわることじゃない」と考えてみようをオススメしたいです。
何か子どもにできるようになってほしい!と思ったら、まず意識を向ける対象を立てることはすごく大事だと思います。
意識を向ける対象が絞られるので、ただ指摘して終わりではなく、次に子どもの行動が良くなったときなどに気づきやすくなります。
ステップ③:自分の正しい論に気づける人が強い
正しい論を手放すのは難しいです。 したがって、「正しい論を手放すことは無理でも、自分の正しい論に気づくこと」がゴールです。
「今子どもに要求していることは、自分の正しい論からくるこだわりかもなぁ」こう気づけたら、関わり方や声かけなどが色々てきます。
ここまでの意識ができたら、正しい論を手を放さなくても、子供に否定的な意識を持たせないダメ出しなどが無意識にを抜いているものです。
【まとめ】完璧でなくていい。意識することが大事
私は『完璧に何かができるよりも意識できること』これが子育ての実践としては最高の状態だと思います!
- 脳の癖:人間の脳は大きく注目し、記憶しやすい。
- ダメ出しの影響:安易なダメ出しは、子どもの挑戦や決断の決断を上げてしまう。
- 対策① 決めつけない:行動の裏にある事情を聞くことで、不要なダメ出しを減らす。
- 対策② 未来志向:「なんでやったの?(過去)」ではなく「次はどうする?(未来)」と問いかける。
- 対策③ 正しい論と向き合う:自分のこだわりを棚卸し、優先順位をつける。手を放さなくても「気づく」だけでOK。
ぜひできる限り正しい論と検討してみてくださいね!応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
幼児教育講師TERUでした。