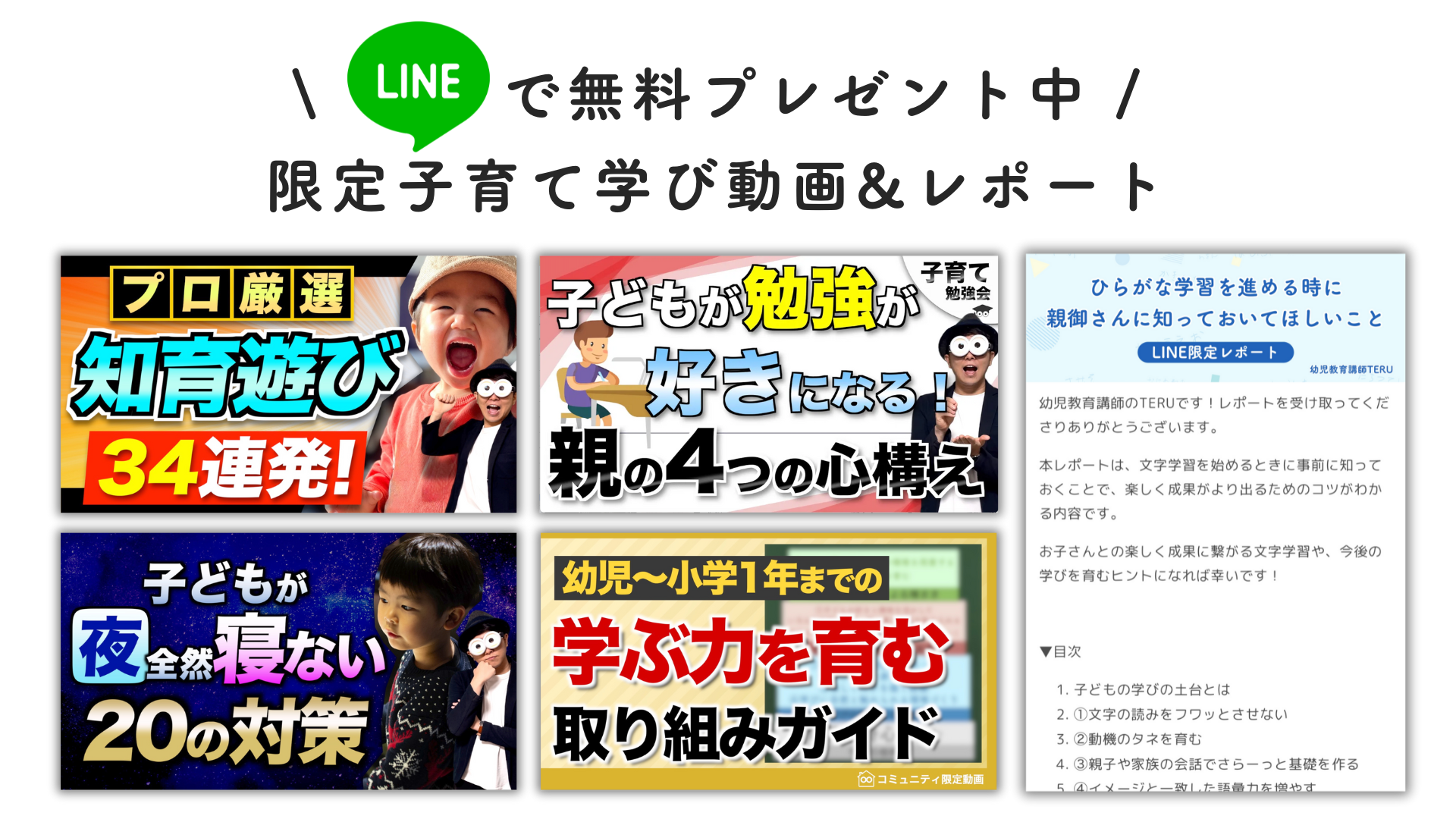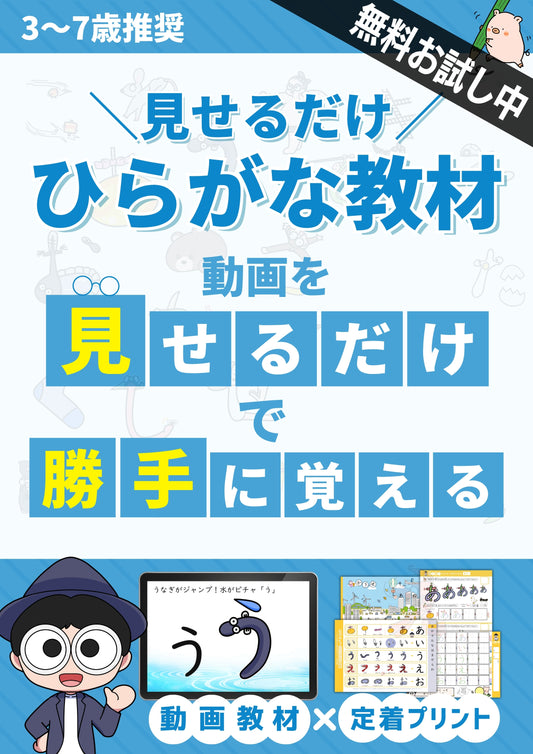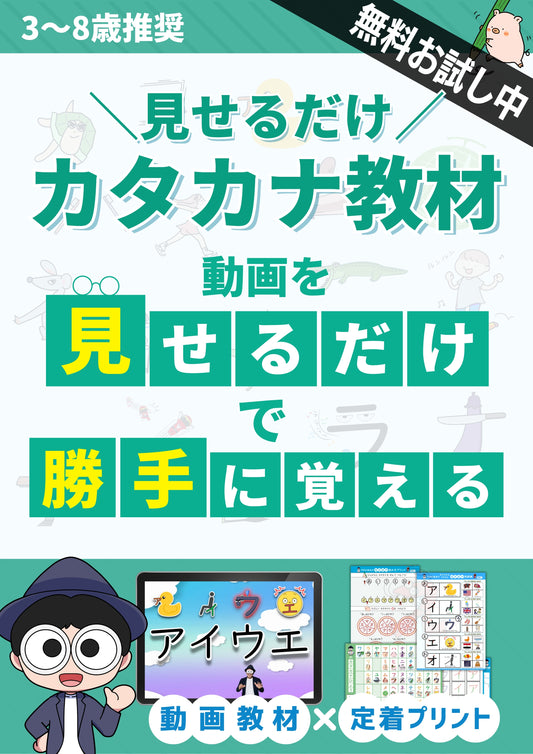幼児教育講師のTERUです。
「子どもの抱っこのしすぎは良くないと聞くのですが、本当でしょうか?」
これは多くの方が気になることだと思います。
もしそのような疑問を持たれているのであれば、次の2つの研究について知っておいてほしいです。
【目次】
- 抱っこと遺伝子の関係についての研究
- 抱っこの「タイミング」に関する研究
- 現実の子育てでどう考える?
- 早くから保育園に預けている場合は?
❶ 抱っこと遺伝子の関係についての研究

まず知っておいてほしいのが、2017年にカナダのブリティッシュ・コロンビア大学が発表した注目の研究です。
この研究では、生後5週目の赤ちゃんを育てているお母さんたちに、どれくらい赤ちゃんとスキンシップをしているかを日記につけてもらい、その子どもたちが4歳半になったときにDNA(遺伝子)を分析しました。
その結果、スキンシップが多かった子どもほど、
- 免疫機能
- 代謝機能
などに関わる遺伝子に良い変化が現れていたのです。
この研究が示したのは、
「肌に触れるスキンシップが、赤ちゃんの遺伝子レベルにまで良い影響を与える」
という、幼児教育界でも結構インパクトがある研究結果でした。
ちなみにこれはマウスの研究でも確認されています。赤ちゃんマウスに親が頻繁に毛づくろいなどのスキンシップをすると、ストレス関連遺伝子に変化が生まれ、成長後もストレス耐性が高まることがわかっています。
この仕組みは、発達心理学で言われる「愛着形成」にも深く関係しています。
つまり、抱っこは、子どもの脳・体・心を育てる上で不可欠な行為であり、「遺伝子レベル」にまで影響するということですね。
だからこそ、「抱っこしすぎかな?」なんて気にせず、たっぷりの愛情で、お子さんを抱きしめてあげてくださいね。
ちなみに、愛情表現の方法は抱っこだけではありません。年齢に応じたいろんな方法があります。それについては以下のYouTube動画で解説していますので、よかったらご覧くださいね。
❷ 抱っこの「タイミング」に関する研究

次に注目したいのが、“どのタイミングで抱っこするか”が子どもの発達に与える影響についての研究です。
あるサルの親子を対象とした研究では、
- 親がずっと抱っこしている子どものサル → ストレスに弱く、対処がうまくできない
- 1週間に1時間だけ親と離れた子どものサル → ストレスに強く、前頭前野が発達
また、マウスの実験でも、1日15分だけ親と離された子どもの方が、よりストレスに強くなるという結果が得られています。
「抱っこを求められてすぐ応じるよりも、少し我慢させてから抱っこする方が、ストレス耐性が高まる可能性がある」
ただし、ここで大事なのは“バランス”です。引き離す時間が長すぎると逆に不安が強くなることがわかっています。
結論としては、「優しさと、ほんの少しの“我慢”」をバランスよく取り入れることが、子どもの健全な発達につながると考えるのが良いですね!
❸ 現実の子育てでどう考える?

ここまで読むと、「毎回タイミングを調整しないといけないの?」と感じる方もいるかもしれません。でも、そんなに厳密にやる必要はまったくありません!
- 抱っこを求められてすぐ応じるときもあっていい
- ときには少しだけ待ってもらうときがあってもいい
このくらいのゆるやかな意識で大丈夫です。
そもそも、毎日忙しく過ごしている中で、すぐ抱っこする余裕がない場面の方が多いですよね?
だからこそ、「できるときはすぐに抱っこしてあげる」というシンプルな意識だけでも十分です。
❹ 早くから保育園に預けている場合は?

今回のようなテーマの話をすると「保育園に預けているから、抱っこする時間がそもそも少ない…」そんな声もよく聞きます。
まず安心してほしいのは、
- 保育園の先生も日々お子さんに対してスキンシップを取ってくれています
- 愛着は親以外の大人との関係でも形成されることが分かっています
保育園では子どもが「抱っこして」と思っても、すぐに応えてもらえるわけではありません。
ですから、ご家庭では「あえて抱っこしない」という意識は持ちすぎず『できる時はすぐに抱っこしてあげる』『抱っこのしすぎについては考えない』で良いと思っています。
もちろん仕事が終わって帰ってきた後の時間でのスキンシップはすんごくしんどいですし、仕事と家事で今詰めた平日の後の土日の家族時間も、疲れが取れずスキンシップがしんどいこともあると思います。
僕は親が無理しすぎる子育てというのは、それはそれで回り回ってお子さんにも良くない影響が生まれてしまうと思っているので、ぜひ
できる限りできる範囲の中で『できる時はすぐに抱っこしてあげる』
そんなスタンスでお子さんと向き合ってほしいなと思います!
ということで、今回は、「子どもの抱っこのしすぎは良くないのか?」という疑問に対して、2つの研究をご紹介しました!
少しのご参考になれば嬉しいです!最後までお読みいただき、ありがとうございました。