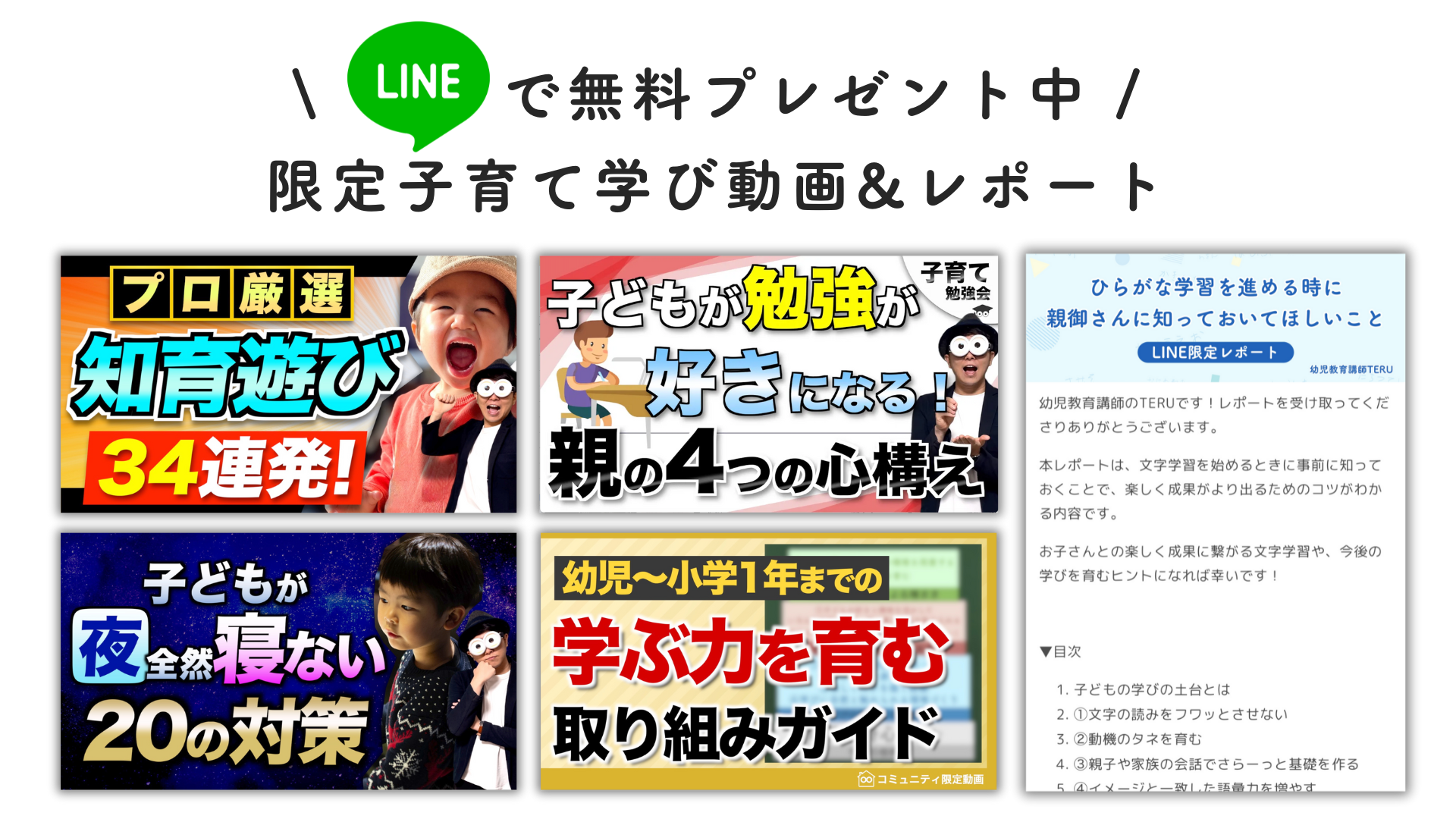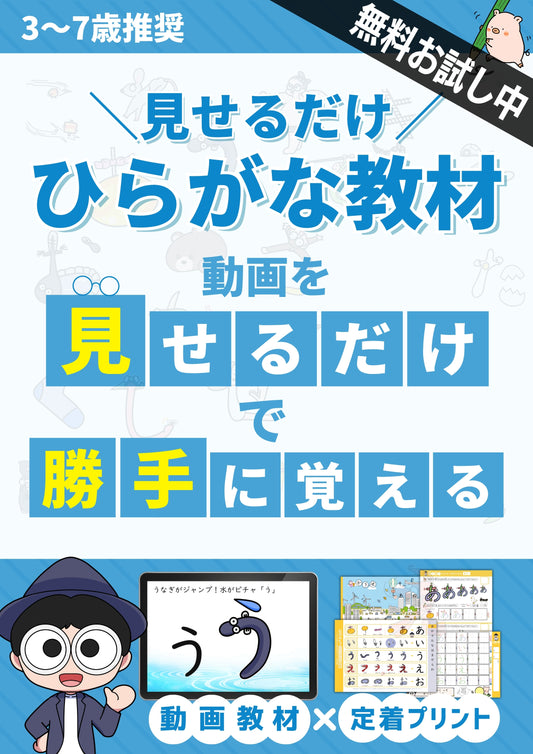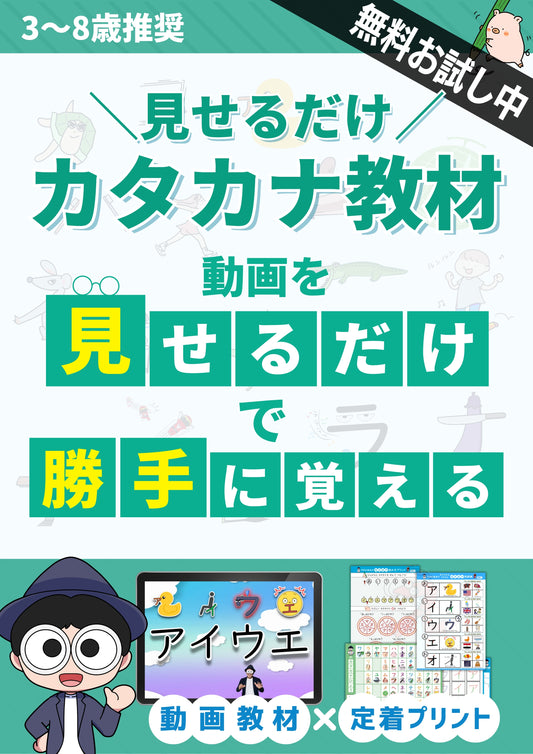今日は、世界が注目する最強の思考法『クリティカルシンキング』について、子育ての観点から皆さんと考えていきたいと思います。
「クリティカルシンキングって何?」という方にも分かりやすく、その育て方から親が子育てに活かす方法までお話ししますので、ぜひお付き合いください。
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
2~12歳【子どもが身につけたい思考法No1!】子育てにクリティカルシンキングを取り入れる方法 / 子育て勉強会TERUchより【目次】
- そもそも「クリティカルシンキング」とは?
- 「ロジカルシンキング」との違い
- 子どものクリティカルシンキングを育む2つの方法
- 親が「子育て」に活かす2つの方法
- 最も大事な、最後の考え方
- 【まとめ】「当たり前」を疑う最強の思考法
そもそも「クリティカルシンキング」とは?
クリティカルシンキング(Critical Thinking)は、数年前「世界のビジネススキルランキング」で2位になるほど注目されているスキルです。
日本語では『批判的思考』と訳されがちですが、これは誤解を招く表現です。
本当の意味は『知識や経験に囚われずに物事の本質を見極めていくこと』です。
私たちは「これまでこうしてきたから」「みんながそうしているから」という理由で、それが本当に正しいのか、必要なのかを考えないまま行動してしまうことがあります。
そんな「当たり前」に捉われず、俯瞰して本質を考える思考法こそが、クリティカルシンキングです。
変化の激しいこれからの時代、今までの知識や経験だけで物事を判断していては、すぐに取り残されてしまいます。だからこそ、自分の常識や当たり前を疑うこのスキルが、非常に重要だと考えられています。
「ロジカルシンキング」との違い
この2つは混同されがちですが、役割が違います。
ロジカルシンキング(Logical Thinking)とは、物事を筋道立てて考え、説明する「ツール」です。
- 例:【論点】問題行動を解決したい → 【結論】絵本で情操教育を行う → 【理由】絵本が好きで、行動を学ぶきっかけになるから。
クリティカルシンキング(Critical Thinking)とは、その筋道を俯瞰して疑い、精度を高める「考え方」です。
- 例:「そもそも、その問題行動は今、解決すべきもの?」「絵本以外の選択肢は?」「絵本にデメリットはない?」
ロジカルシンキングが「AからBへ進む力」だとしたら、クリティカルシンキングは「そもそもBに向かうのは正しいか?」と考える力です。
子どものクリティカルシンキングを育む2つの方法
では、どうすれば子どもの中にこの思考法が育っていくでしょうか?
僕は、シンプルなことの積み重ねだと思っています。
1. 今の「当たり前」を疑う問いかけをする
問いを立てる力は、ほぼ「習慣」です。「もっと良い方法はないか?」「これは本当に正しいのか?」と考える経験を積む必要があります。
日々の勉強やお手伝いに対して、「今のやり方よりもっと良い方法はないか?」と親子で一緒に考える習慣が、クリティカルシンキングの土台を作ります。
2. 日々の中で「選択の理由」を聞き、話す
子どもは日々、何となくで物事を選んでいます。これは「思考停止状態」に近いです。
たまにで良いので、子どもが何かを選んだ時に「どうしてそれを選んだの?」と理由を聞いてあげてください。
大した理由でなくても構いません。「自分がなぜその選択をしたのか」を意識に向けることこそが、思考停止から抜け出す第一歩です。
また、「お父さんはこういう理由で、これを選んだよ」と、親が自分の思考プロセスを話してあげるのも、子どもにとって良い見本となります。
親が「子育て」に活かす2つの方法
子育てにこの思考法を取り入れすぎるのは、かえって不安を招くので注意が必要です。
子育て方針という「大きなもの」を疑うのではなく、日々の「具体的なこと」に活用するのがオススメです。
1. 子どもへの「常識」や「思い込み」を取り払うために使う
私たちは、自分の経験から「勉強とは我慢してやるものだ」「良い大学に行くべきだ」といった“常識”を子どもに強要してしまうことがあります。
「でも、それって本当に正しいのか?」「今の時代や、この子に合っているのか?」と一度立ち止まって考える。
この思考が、親の思い込みから子どもを解放し、その子の可能性を広げることにつながります。
2. 自分の「いらないこだわり」を手放すために使う
子育ては忙しく、完璧主義な人ほどパンクしがちです。
そんな時こそ、「本当にこの家事は今すぐ必要?」「これって問題行動に見えてたけど、この子の長所かも?」とクリティカルシンキングを使うことで、抱えすぎているこだわりを手放す助けになります。
最も大事な、最後の考え方
ここまでクリティカルシンキングの重要性をお話ししてきましたが、最後に本質的なことをお伝えします。
それは「クリティカルシンキングにこだわればクリティカルシンキングじゃなくなる」ということです。
これ伝わりますでしょうか?僕の中ではかなり本質的なことなので、伝わっていると嬉しいのですが、多分、クリティカルシンキングができている完璧な状態なんてありませんよね。
「クリティカルシンキングを完璧にしないと!」と執着すればするほど、その考え自体に柔軟性がなくなり、盲目的になってしまいます。これはまさに、ここまで一緒に学んできたことと正反対のことですよね。
この思考法にすらこだわりすぎず、『できる限りできる範囲で!』という考え方のもと、活用していくのが一番大切です。
【まとめ】「当たり前」を疑う最強の思考法
今回は、世界が注目する「クリティカルシンキング」について、子育ての視点から解説しました。
- クリティカルシンキングとは:「当たり前」を疑い、物事の本質を見極める思考法。
-
子どもに育む方法:
- 「もっと良い方法はない?」と当たり前を疑う問いかけをする。
- 「どうしてそれを選んだの?」と選択の理由を意識させる。
-
親が活用する方法:
- 「良い大学に行くべき」など、自分の常識(思い込み)を疑い、子どもの可能性を広げる。
- 「この家事は本当に必要?」と、いらないこだわりを手放すために使う。
- 最も大事なこと:「クリティカルシンキング」自体にもこだわりすぎないこと。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。