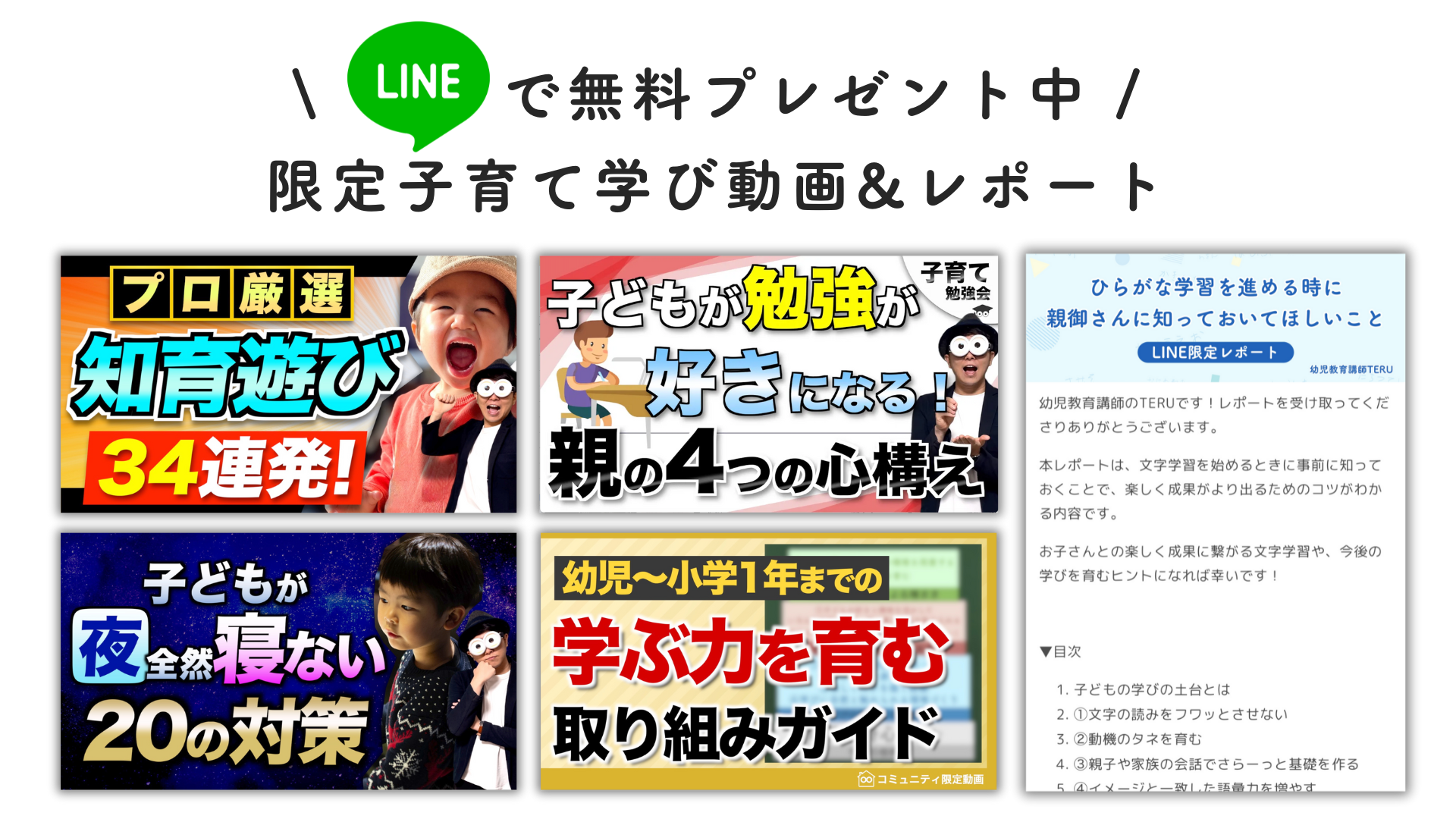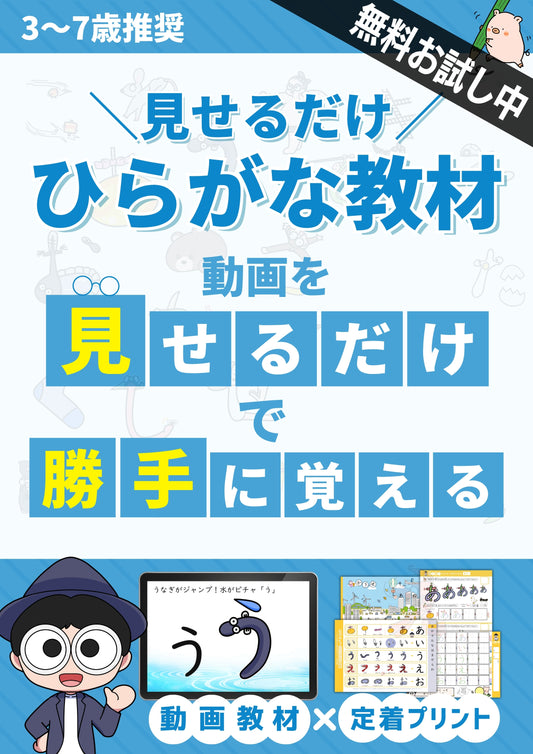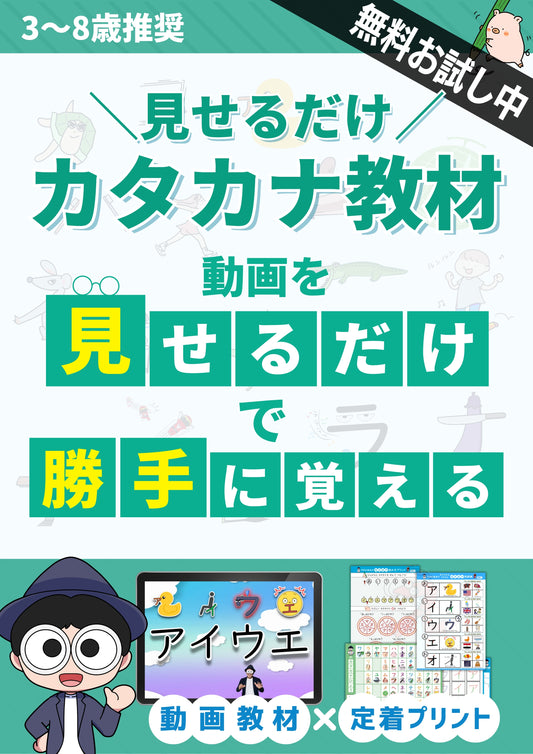「子どもには勉強苦手にはなってほしくないと思っています。親として知っておいた方がいいことや、できることはありますか?」
これは多くの方にとって関心ごとかもしれませんね。
脳科学の観点から解説してみたいと思います!
【目次】
- 脳科学的に、勉強苦手ってどういう状態?
- 勉強苦手になりやすい構造①:「わからない・間違える」が、脅威と直結している
- 勉強苦手になりやすい構造②:「ドーパミンが出るポイント」が少なすぎる
- 【まとめ】脳の悪循環を断ち切る
脳科学的に、勉強苦手ってどういう状態?
 脳科学の視点では、子どもの勉強嫌いは、「特定の脳の回路が、ネガティブな方向に強く強化されてしまった状態」と説明ができます。
脳科学の視点では、子どもの勉強嫌いは、「特定の脳の回路が、ネガティブな方向に強く強化されてしまった状態」と説明ができます。
勉強苦手には、大きく分けて、脳の中の2つのシステムが関わっています。
①「嫌だ・怖い」と感じる扁桃体のシステム
扁桃体は、脳の「警報装置」のような役割をしています。勉強をする中で「わからない」「叱られた」「失敗した」といったネガティブな体験が繰り返されると、この扁桃体が強く反応し始めます。
そして、「勉強そのもの=脅威(ストレス)」だと学習してしまうわけです。こうなると、いざ勉強を始めようとするだけで、自動的に扁桃体が興奮して、ストレスホルモンが分泌されます。
このストレス反応の厄介なところは、思考とか理性とかと大きく関わる脳の「前頭前野」の働きを抑制してしまうことですね。人は、前頭前野がうまく働かないと、一時的に情報を記憶したり処理したりする「ワーキングメモリ」の働きが悪くなってしまいます。
その結果、普段なら解けるはずの簡単な問題すら、頭が真っ白になって解けなくなってしまうんですね。これが「苦手」意識の正体の一つです。
②「やりたい!」を生み出すドーパミンシステム
人の脳は「できた!」「わかった!」という成功体験を積み重ねると、快楽物質であるドーパミンがドパドパ出ます。このドーパミンこそが、「次もまたやりたい」という意欲の源泉であることはみなさんご存知だと思います!
そして、勉強しても「わからない」「間違える」という体験ばかりが続いてしまうと、このドーパミンは残念ながら放出されません。脳は、「勉強という行動」と「喜び」をうまく結びつけることができなくなってしまって、その結果、勉強に対する意欲そのものが失われていってしまうわけです。
以上をまとめると、「勉強が苦手になる」というのは、
- 扁桃体の恐怖回路が過剰に作動して前頭前野の思考回路を停止させてしまい、
- さらにドーパミンの意欲回路が作動しなくなってしまう
という脳の悪循環が「自動化」されてしまう現象ということですね。
ではここから、この脳の仕組みを踏まえて、勉強苦手になりやすく、気をつけていきたい点について2つ挙げてみます!
勉強苦手になりやすい構造①:「わからない・間違える」が、脅威と直結している
 勉強が苦手になりやすいご家庭では、
勉強が苦手になりやすいご家庭では、
👦わからない
→「ちゃんと考えたの?と問い詰められる」👦間違える
→「この前やったところじゃん!と何度同じミスをするの?」と叱られる
→「お友達の〇〇ちゃんはすぐにできるようになったって言ってたわよ!」と比較される
というように、子どもの「できない状態」が「親の不機嫌」や「叱責」、「周りとの嫌な比較」という脅威に直結しやすい傾向があります。これでは、脳が「間違えること=危険!」と学習してしまいますよね。
一方、苦手になりにくいご家庭では、子どもが「わからない」と言ったり、テストで悪い点を取ったりした時、例えば、
「お、そうか!どこでつまずいたか一緒に見てみようか」
「あー、そこ難しいよね。わかるわかる。」
「これは悩むね。いいところに気がついたね。」
「そっか、わからんか。大丈夫、大丈夫。どこまでは『わかる』か、そこだけ教えてくれる?」
「よし、じゃあ一緒にやっつけようか。どこから手伝おうか?」
など、否定せずに安心できる声かけをしています。これによって、子どもは「わからない」状態になっても扁桃体が過剰に興奮しないで済み、前頭前野がシャットダウンしにくいんです。
まぁこれは、そんなことわかっているよ!という内容かもしれませんが、このような声かけを自分のものにするのが難しいんですよね。もうこれは親側のトレーニングと思って頑張るしかないなと僕は思ってます。
子どもに対してだけではなく、家族や仕事仲間でも、失敗や間違いに対してポジティブな反応をできる意識をしながら、自分の習慣にするのがオススメですね!僕も頑張ります。
勉強苦手になりやすい構造②:「ドーパミンが出るポイント」が少なすぎる
 勉強の意欲の源泉がドーパミンであることは、前半でお話ししましたが、勉強が苦手になりやすいご家庭では、ドーパミンが出るポイントが「結果」しかないケースが多いです。例えば、テストで良い点数を取った。宿題を終わらせることができた。これらは、取り組んだ最後に訪れる結果です。
勉強の意欲の源泉がドーパミンであることは、前半でお話ししましたが、勉強が苦手になりやすいご家庭では、ドーパミンが出るポイントが「結果」しかないケースが多いです。例えば、テストで良い点数を取った。宿題を終わらせることができた。これらは、取り組んだ最後に訪れる結果です。
これらが良い結果であれば、ドーパミンが出て、「次も頑張ろう!」と思えるものですが、結果は、毎回良い結果ばかりではありません。毎回良い点数が取れるわけではないし、宿題が難しくて、うまく終わらせられないこともありますよね。
脳には、『報酬予測誤差』と呼ばれる概念があり、脳は常に「このくらいやったら、このくらいの報酬が来るだろう」と予測しています。それを下回る結果が続くと、ドーパミンは出ずに、不快感が強まってしまって、結果として「やっても上手くいかない」と勉強の意欲が低下してしまうことがあります。
そうならないために、最終的な結果以外にドーパミンが出るポイントを増やしてあげるのが大事なんですね。
大きく分けると3つあるので1つずつご紹介します!
1)自分で決めた感でドーパミンポイントを増やす
人は、「誰かにやらされた」と感じた瞬間にやる気を失うのは皆さんご理解されていると思います。これは、自分の行動を自分でコントロールできているという感覚が、脳にとって本質的な報酬(ドーパミンが出るポイント)だからです。
なので、親がすべきことは「簡単なことでOKなので選ばせること」です。これを「マイクロ・エージェンシー(小さな主体性)」と呼んだりします。
例えば、
- 「宿題、いつやる? ご飯の前? それともお風呂の後?」
- 「算数と漢字、どっちから先にやっつけたい?」
- 「このドリル、今日は3ページやる? それとも4ページ頑張ってみる?」
- 「終わったら、お母さんに『終わった!』って報告しに来る? それとも自分で丸付けまでする?」
重要なのは、どちらを選んでも「やる」ことには変わりない、という絶妙な選択肢を提示することですね。子どもは「やらされる」のではなく「自分で選んだ」と脳が認識するため、行動への抵抗感(扁桃体の興奮)が減り、主体的に取り組む意欲(ドーパミン)が湧きやすくなります。
2)達成の細分化でドーパミンポイントを増やす
ドーパミンは、「目標を達成した時」にも放出されます。 この「達成感」を、より強く、より頻繁に感じさせるための工夫が「細分化」です。
勉強が苦手な子は特に、「どこまでやれば終わりなのか」という全体像が見えていないために、脳が「終わりのない苦痛」と感じてしまいがちです。
そこで、やるべきタスクを「視覚化」して、完了を「見える化」することで、達成感を細分化します。一番簡単なのは、小さな付箋です。「かんじドリル 1ページ」「けいさんカード 3かい」「おんどく」といったタスクを、付箋1枚に1つずつ書きます。それを「やることボード」や「ノート」でもどこでもOKなので、決めた場所に貼っておきます。
そして、1つ終わるたびに、子ども自身がその付箋をはがし、「おわった!」の場所に移動させるというルールにします。この、「自分で付箋をはがして、終わった!の場所に貼る」という物理的な行動。 これが脳にとって、「タスクを一つ、自分の力で完了させた」という明確な合図になります。この瞬間に、プチ達成感としてドーパミンが出るんですね。これが積み重なると、脳は「タスクを終わらせる(付箋を移動させる)こと=快感」と学習していきます。
3)「難しい!」を「脳が育つシグナル」と再定義してドーパミンポイントを増やす
多くの子は、「わからない」「難しい」と感じた瞬間、それを「失敗」や「苦痛」と捉えてしまいがちです。これはまさに扁桃体が「脅威だ!」と反応するシグナルになります。
ですが、脳科学の視点では、この「難しい!」「悩ましい!」と感じている瞬間こそが、脳が新しい神経回路を必死に作ろうとしている、まさに「成長している」瞬間と言えます。
勉強が苦手になりにくいご家庭では、この「難しい!」という感覚の「ラベリング(意味付け)」を変えるのが非常に上手です。
例えば、子どもが「あー!これ難しい!」とイライラし始めたとします。 ここで、「頑張れ!」や「1問だけやってみよう」でもいいのですが、もっと強力なのは、その「感覚」を承認することです。
「お!いいね!今、脳が一番育ってる瞬間だ!」
「その『難しい!』って感覚、脳が新しい道を作ろうとしてる証だね。」
「それだけ悩めているってことは、ちゃんと深く考えてる証拠だね。」
これは、発達心理学の権威であるキャロル・S・ドゥエック博士が提唱する「成長マインドセット」の核となる考え方です。
この声かけの何が良いかというと、「難しい」という苦痛(扁桃体のシグナル)を、「脳が育ってる!」という報酬(ドーパミンのシグナル)に、その場で「意味変換(再ラベリング)」している点です。
これを繰り返していくと、子どもは「難しい!=苦痛」ではなく、「難しい!=成長の快感」と脳が少しずつ学習し始めます。 すると、「難しい問題に取り組む」という行動そのものがドーパミン放出のトリガーになっていくことがあるんですね。
そして、今のように実際に「難しい!」と感じているときの声かけも大事ですが、僕がもっと大事だと思っているのが、日々の中で今のような考え方を何度も伝えていくことです。
僕が運営するTERU先生の動画教室という、子ども向け教育動画が使いたい放題のオンラインサービスがあるのですが、そこでは、動画やプリント教材とは別に、僕が毎週子どもたちにお手紙を書いてるんですね。
その手紙は、まさにお子さんの成長マインドセットにつながる考え方を教えることを1つの目的にしています。
例えば、過去に書いた手紙のテーマでは、
- 脳は難しいことに挑戦するときに成長する脳科学のお話
- できない。難しいと思ったら成長のチャンスと捉えるお話
- 頭の良い人は裏でどんな努力をしているのか?のお話
など、いろんな視点から難しいことやできないことに挑戦する意味を伝えていっています。
こんな感じで、ぜひ何気ないお子さんとの時間の中で、難しいことやできないことをどう捉えるといいか?をお子さんに伝えたり、一緒に考えてみて欲しいです。
繰り返し考えるきっかけを作っていくからこそ、実際に難しいことと出会った時に、ポジティブな考えが第一想起されて、ポジティブな行動ができるようになっていくわけです。
【まとめ】脳の悪循環を断ち切る
ということで、以上長くなりましたが、振り返ると、
- 勉強苦手になりやすい構造①:「わからない・間違える」が、脅威と直結している
- 勉強苦手になりやすい構造②:「ドーパミンが出るポイント」が少なすぎる
ドーパミンポイントを増やすためには
- 自分で決めた感でドーパミンポイントを増やす
- 達成の細分化でドーパミンポイントを増やす
- 「難しい!」を「脳が育つシグナル」と再定義してドーパミンポイントを増やす
というお話でした!少しでも参考になれば嬉しいです!
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。