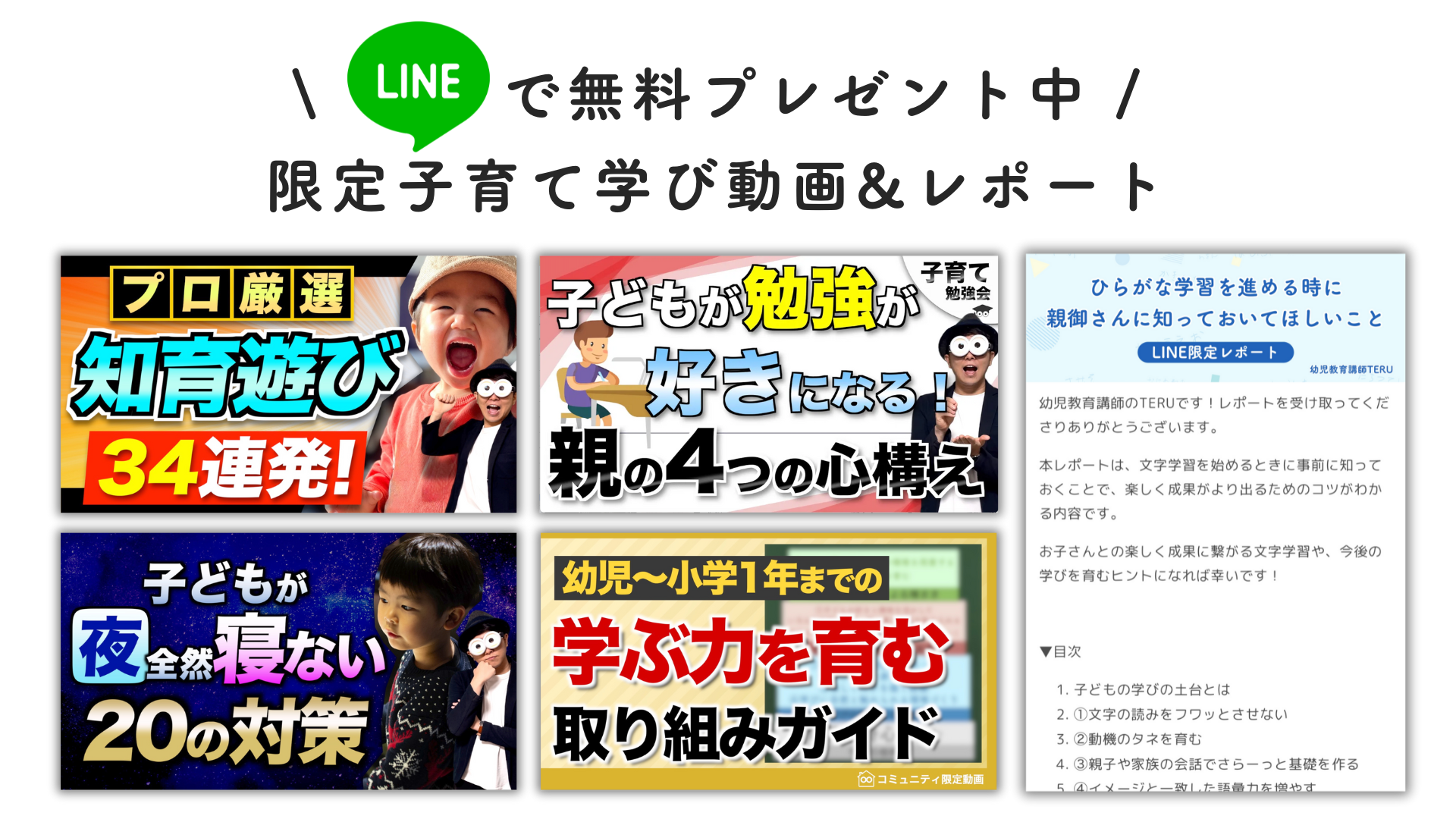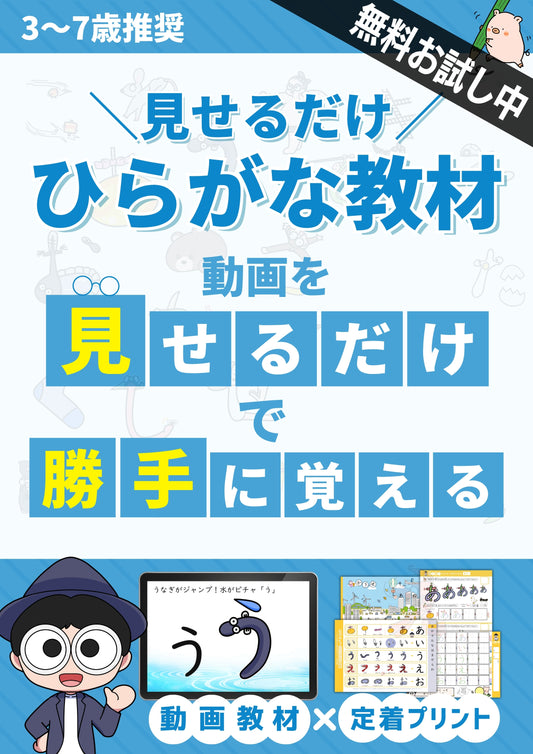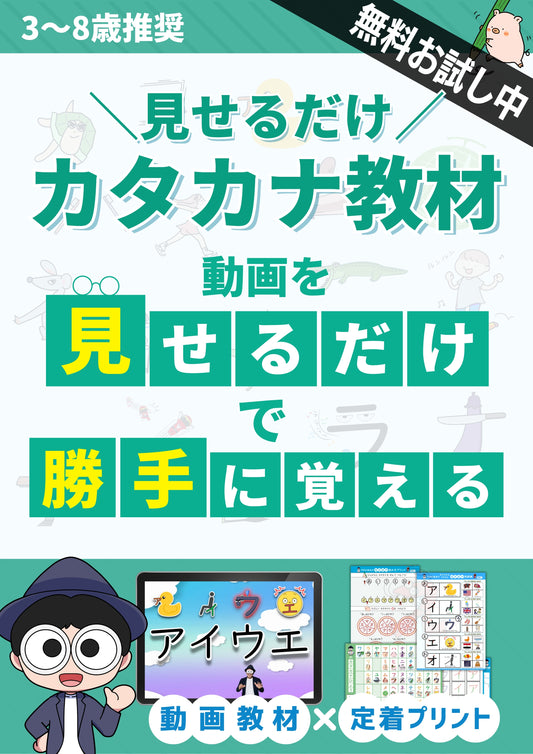多くの親御さんは「子どもには勉強が得意になってほしい」あるいは「得意ではなくても人並みについていけてほしい」「勉強嫌いや苦手にはなってほしくない」そう思っているのではないかと思います。
今日は、僕がこれまで多くの親子をサポートさせてもらってきた経験から、『勉強が苦手・嫌いにならない家庭の特徴3選』をご紹介させていただきます!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
3~10歳【幼児教育講師が厳選】子どもが勉強が苦手・嫌いにならない家庭・親の特徴 / 子育て勉強会TERUchより【目次】
- ① モチベーションが上がる「魔法の方法」はないと知っている
- ② 「できた!わかった!」がモチベーションの源泉だと知っている
- ③ 「勉強しなさいと言わなければ勉強するようになる」は幻想だと知っている
- 【まとめ】勉強を「好き」にするための環境づくり
モチベーションが上がる「魔法の方法」はないと知っている
 よく、子どもの勉強のモチベーションを上げる最も効果的な方法を教えてください!と聞かれるのですが「そんなのない」というのが答えだよなぁって思いながらいつも言葉を紡いでいます。
よく、子どもの勉強のモチベーションを上げる最も効果的な方法を教えてください!と聞かれるのですが「そんなのない」というのが答えだよなぁって思いながらいつも言葉を紡いでいます。
そもそもモチベーションって色んな要素が複雑に絡み合っていて、複数の条件や要素が揃ったり積み重なったりしたときに「よし勉強をしよう!」と思うのが人です。
例えばですが、子どものモチベーションを上げるかもしれない要素を挙げてみますね。
- 何か勉強した結果得たい目標がある
- 行きたい学校などが明確にある
- 教材のレベル感が自分に合っていてできそう!と思える
- 達成したことを気にかけてくれて声をかけてもらえる
- 逆にされたくない余計な口出しをされない
- 周りに集中を阻害するものがない環境である
- 周りに当たり前に頑張っている人がいて自分も頑張らないと!と思える
- 好きな文房具などを買って使いたい!と思えている
- 自分で、やる教科を選ぶなどやらされている学習ではない
- 良い点数が取れて嬉しい・悪い点数で悔しい
- その教科や先生が本質的に好き
- 毎日やることが当たり前になっていて少ないモチベーションで取りかかれる
- 睡眠や栄養がしっかりと取れている
- 部屋の模様替え、自分の机の購入など環境が変わった
- 勉強の順番として最初にサクサクと進んで早く達成を味わえるものから始める
- タイマーなどを使って早く終わらせるという気持ちを高める
- 勉強を一定量終えたらちょっとしたご褒美がある
- アプリなどゲーム感覚で取り組める環境がある
- 親が自分のできていない部分ではなくできている部分を見てくれる
- できた!わかった!という体験が増えて嬉しい
ざっと挙げただけでも、これだけの要素が考えられます。
ここで大事なのは、色んなモチベーションを上げるかもしれない要素があるという前提に立った上で『今の我が子に合う方法を想像すること』です。
子どもの勉強サポートが上手な親御さんはその想像を大切にされています。具体的にはまず「これまでこの子が頑張れたタイミング、頑張れた環境、頑張れた関わり方、頑張れた取り組み方、頑張れたきっかけ」について考えてみることです。
これまでの子どもの姿にはたくさんの『頑張れる理由』が溢れています。何かを頑張れたとき「この子には何があったんだろう?」と想像してみることで、数多ある勉強サポートの選択肢から、この子に合うかもしれない選択肢が少しずつ見えてきます。
それがちょっとずつ見えてきたら、あとはその環境や関わり方、きっかけ作りをこれまた少しずつ試してみる。それが僕たちができることだと思います。
「できた!わかった!」がモチベーションの源泉だと知っている
 ①で色々と要素を挙げましたが、僕の経験から多くの子にとってモチベーションになりやすい方法は『できた!わかった!』を積み上げていくこと。やっぱりこれだよなって思ってます。
①で色々と要素を挙げましたが、僕の経験から多くの子にとってモチベーションになりやすい方法は『できた!わかった!』を積み上げていくこと。やっぱりこれだよなって思ってます。
「とにかく数が好き!数を見ているだけでハァハァしてしまう」なんて稀なケースを除けば、多くの子は「できた!わかった!」という喜びが取り組むモチベーションの源泉になります。
そう考えると、僕たちがすべきは「子どもができた!わかった!と思える機会をどう作るか?」ですよね。
できることを2つ挙げますね!
1) 周りの進捗に子どもを合わせるのではなく、子どもの理解度に取り組むものを合わせる
これはわかりやすいですね。でも重要です。例えば、子どもが今すでに学校の算数の勉強についていけていないとします。
このケースで取るべきサポートは『今学校でやっている内容よりも少し前に戻って理解を深めていく』ということですよね。
算数は特に、前の単元の応用や組み合わせで解ける問題が多々ありますから、理解できていない中で次に進むとどんどん沼にハマるようにわからなくなっていってしまいます。
ですが、この『少し前に戻って理解を深めていく』という選択を取るのが中々難しいですよね。親としては「周りの進捗に遅れたくない」と思ってしまいますよね。
でも、どこまでいっても大事なのは、子どもが「できた!わかった!」を積み上げることです。
今の単元のハードルが高すぎるのであれば、今の子どもにとっては「できない。わからない」を積み上げているだけの学び体験になっている可能性は高いです。
そうならないために子どもの理解度に合ったレベルでの単元や教材を用意してあげて、まずは「できた!わかった!」を味合わせてあげる。
そうやってその子なりのペースを大事にしてあげながら、1つ1つ「できた!」を感じることができれば、確実に自信は増えていって、そこから「次の単元も頑張ってみる!」というモチベーションが湧くわけです。
2) 今の理解度を細分化して「できてるね!」を伝えてあげる
これがオススメです!子どもが今の算数の単元が理解できないとしても、全部ができないわけではありません。
「ここまでは理解できているんだけど、ここからがわからない」そうやって、子どものできない。わからないはさらに細分化できることが結構あります。
そういう場合、ちゃんと「ここまでは理解できてるね!いいね」と伝えてあげてほしいです。
子どもはわからないことがあったとき、拡大解釈で「自分はこれはできない!できていない!」と自分に大きなラベルを貼っています。
たった1つの問題ができない!というだけで「自分は勉強ができない!」と思考が飛んでいってしまう子もいるくらいです。そんな脳の癖があるからこそ、「どこまで理解できていてどこから理解できていないか?」を大人が確認してあげて、「ここまでは理解できてるね!いいね」と伝えてあげる。
これが子どもにとってどれほど勇気になるか?はご理解いただけると思います。大変ではありますが、このように細分化して「できてるね!」を伝えてあげる。これも実は子どもの「できた!」という感覚を増やしてあげる大切な関わり方なんです。
「勉強をしなさいと言わなければ勉強するようになる」は幻想だと知っている
 最後はこれです。この言葉。本当によく聞く言葉ですよね。
最後はこれです。この言葉。本当によく聞く言葉ですよね。
『東大生は「勉強しなさい」と言われなかった』そんな文脈でよく聞きますし、僕もそんな発信をしたこともあります。
ですが、この言葉の本質は「勉強をしなさいと言わなければ勉強するようになる」のではなく「勉強しなさいと言わなくてもやりたくなる上手な導き方や環境づくりをしている」ということだと思っています。
多くの子は放置しているだけでは勉強するようにはなりません。
そもそも、多くの子が、机に一定時間向かって何かを取り組むことに苦痛を感じます。では、それを乗り越えられる時とはどんな時でしょうか?それは「できるかも!」あるいは「わかるかも!」を多く感じられるときです。
では、子どもが机の上でより多くの「できるかも!」「わかるかも!」を感じられるにはどうすれば良いでしょうか?それは『机以外での学び体験を上手く作ってあげること』だと思っています。
ちょっと極端なことを言いますが
勉強を苦手にさせる親は『理解できないものを机の上で理解させようとする』
勉強を好きにさせる親は『机以外で理解を育み、机の上で知ってる!できそう!と思わせる』
こんな違いがあると思っています。
勉強を好きにさせる親は『机以外で理解を育むこと』を大事にしています。例えば、子どもの好きなことと学びを組み合わせて、興味のある体験の中で文字や数の力を育みます。
- サイコロを使って数の力を育む
- 積み木遊びで数や図形の感覚を養う
- 外遊びの中で数を数えたり、看板の文字を読んだりする
- 好きなキャラクターや電車、折り紙を通して知育をする
これらを楽しくやってあげている子は、テキストなどでやろうとしていることの理解をまず先に実体験の中で積み上げています。
そして、その後に机の上での学びが始まります。そうなるとどうでしょうか?「これ知ってる!」「これママと遊んだ時のやつだ!」そんな体験が机の上で増えていきます。
これが『勉強をしなさいと言わなくても勉強するようになるカラクリ』です。もちろんこれだけが要素ではありませんが、このカラクリの影響は本当に大きいと思っています。
ぜひ『机以外で理解を育む環境』を少しずつ作っていってあげて欲しいと思ってます。そうすることで、机の上でのできた!体験が確実に増えていくと思います。
【まとめ】勉強を「好き」にするための環境づくり
ということで、最後は駆け足になりましたが、今回のポイントをまとめます。
- 魔法はない:モチベーションを上げるたった一つの方法はなく、子どもの過去の成功体験から「その子に合う方法」を探す。
- 成功体験の積み上げ:周りの進捗ではなく子どもの理解度に合わせて、「できた!」を感じられるレベルから始める。
- 机以外の学び:机の上でいきなり理解させるのではなく、遊びや実体験を通して事前に理解を育み、机の上で「知ってる!できそう!」と思わせる。
これに共感していただける方は、僕と一緒に大事にしていただき、お家ではどんなことができるだろうか?と考えていただけると本当に嬉しく思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。