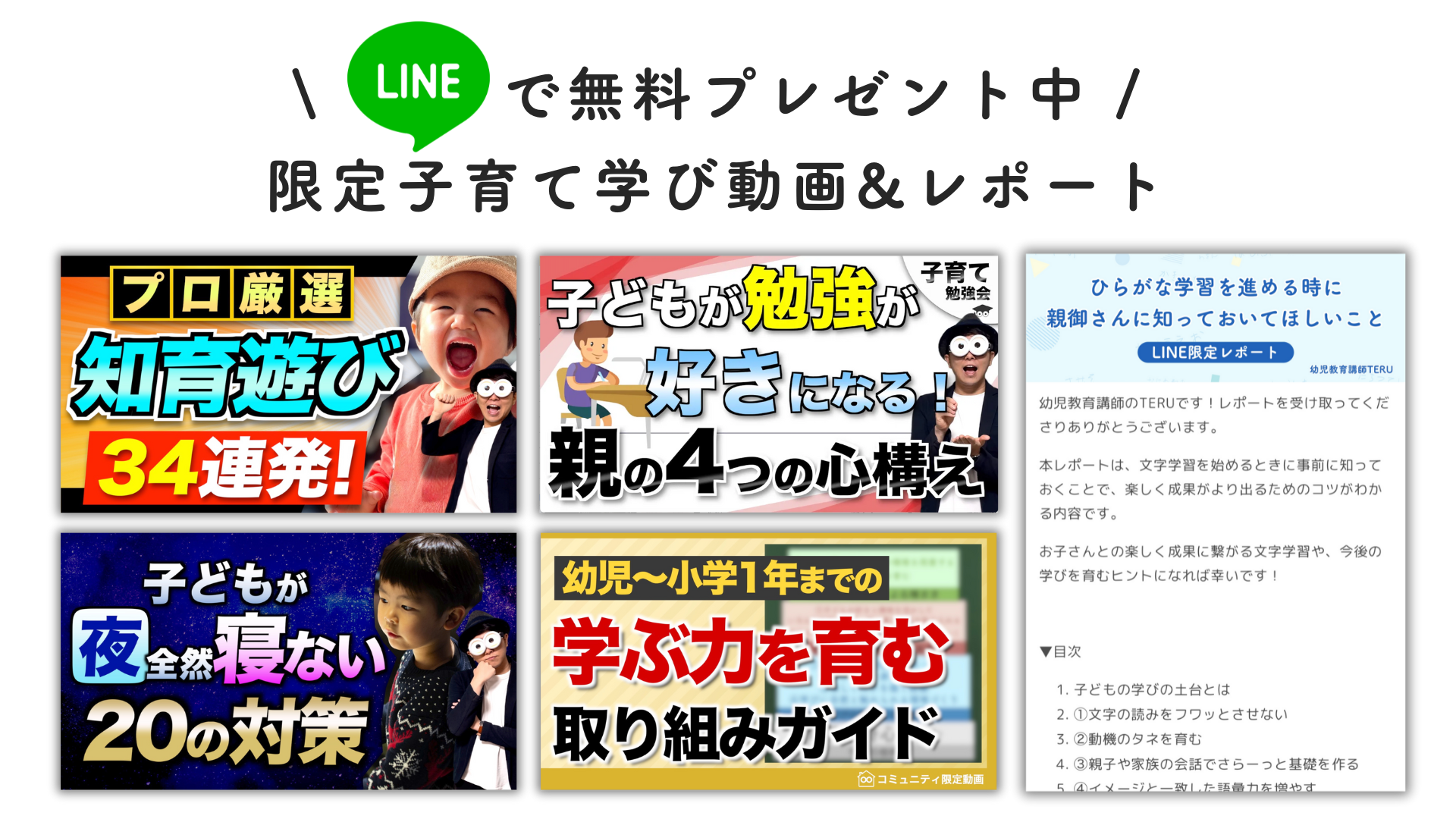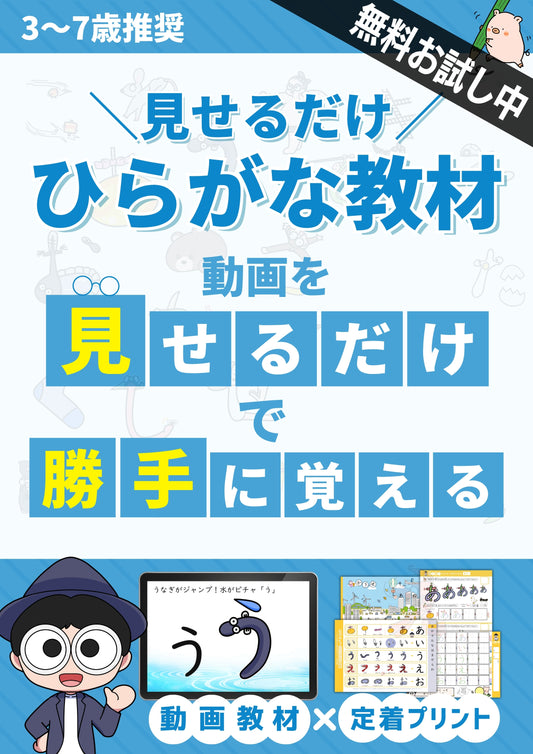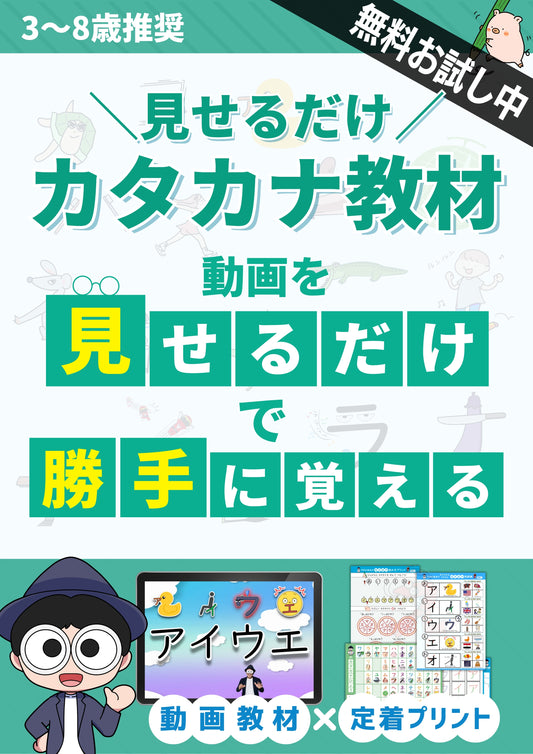「うちの子、家で勉強してたり時々すぐ立ち歩いたり、椅子をガタガタして遊び出したりイライラします。どうしたら集中できるようになりますか?」
これは多くの方が「うちもですー!!!」と共感できる悩みですよね。
この悩み、『生理学的に極めて重要な視点』があるので、ご紹介したいと思います!
この内容を動画(YouTube)で見たい方はこちら
【子育て】親が介入しなくても一人で遊べる子になるためにできること / 子育て勉強会TERUchより【目次】
- ゲームが集中できない原因
- 具体的な関わり方
- この関わり方の最も本質的な部分
- 【まとめ】「ふざけている」ではなく「脳が求めている」
ゲームが集中できない原因
 不安が集中せず、動き出してしまう原因はいろいろありますが、1つ考えられるが『身体の感覚を満たしている』ということです。
不安が集中せず、動き出してしまう原因はいろいろありますが、1つ考えられるが『身体の感覚を満たしている』ということです。
『身体の本能の感覚を満たしている』とはどういうことか。
人間に触れることには、一般的に知られている五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、覚)のほかにも、自分の体をコントロールするために非常に重要で、「隠れた感覚」がいくつかあります。
特に今回のテーマは重要なのが、以下の2つの感覚です。
①固有感覚
これは、筋肉や関節から得られる感覚で、自分の体の位置や動き、力の入れ具合などを脳に伝えています。目をつぶってみても自分の腕がどこにでもわかるのは、この感覚のおかげです。
不安が椅子をガタガタガタしたり、貧乏ゆすりをしたり、鉛筆を強くしたりするのは、無意識に筋肉や関節に圧を加えて、この固有の感覚を刺激しているんですね。
②前庭感覚
これは、「揺れ」や「傾き」あとは「スピード」に関する感覚です。体のバランスを取ったり、姿勢を保ったりするための土台の感覚です。この前庭の感覚も、脳の覚醒レベルと深く楽しんでいます。
例、眠いときに少し歩き回ると頭がすっきりしたり、逆にブランコに心地よく振られるとリラックスしたりするよね。 子どもが勉強中に立ち上がって少し歩き回ったり、椅子を前後に揺らしたりのは、この前の庭の感覚に刺激を入れて、勉強するのに最適な脳の覚醒状態に自分をチューニングしようとしよう、脳の自然な行動なんです。
以上2つの感覚をご紹介しましたが、イメージとしては、子どもたちのためが「感覚のコップ」を持っている感じで、長時間座っていると、特に体を動かすことが好きなお子さんの場合、この「固有感覚」や「前庭感覚」のコップが爆速で空っぽになります。
そして、コップがっぽ空になると、脳は「感覚が足りないよー!満たしてくれー!頼むよー!!」と命令を出してきます。その結果として、椅子をガタガタしたり、立ち歩きしたりというと現れるわけですね。行動は「ふざけたい」という気持ちとか、「集中力不足」という精神論の話ではなくて、「感覚のコップを満たしたい」という、生理現象に近い、自然な脳の働きなんですね。
「考えるとやることはただ1つで、動きたいように動かせてまずは感覚を満たしてあげる方が良いわけです。」
具体的な関わり方
 具体的な対応としては、子どもが立ち上がったり、ガタガタ机をしたりするのが続いたときに、「ちょっと集中が続いているか消えてきてるね。少しだけ立ち上がって、1分くらい体を動かしてきてごらん。」と言って、一応親から体を動かすことを主張して言うことです。
具体的な対応としては、子どもが立ち上がったり、ガタガタ机をしたりするのが続いたときに、「ちょっと集中が続いているか消えてきてるね。少しだけ立ち上がって、1分くらい体を動かしてきてごらん。」と言って、一応親から体を動かすことを主張して言うことです。
この対応方法の良さはいくつかあってですね。
-
脳の癖を活かせる
まずは、人は何かを阻害されれば、さらにしたくなるように脳ができます。
-
その後の親の言葉を受け入れられそうになる さらに
、自分の歩きたい気持ちや体を動かしたい気持ちを認めてもらったことで、そもそもの「仕事をちゃんとしようや」とか「何時までに終わらない」など、別の親の要求を受け入れられるようになる
。
-
時間の枠を半分にした
あとは「1分」などと時間を制限しているのはポイントかなと思います
。
この関わり方の最も本質的な部分
 それは、こう集中ができなくなったら、その原因を知り、自分で対処練習するからです。
それは、こう集中ができなくなったら、その原因を知り、自分で対処練習するからです。
不安はいつか自立して自分で勉強を進める必要があるし、社会に出てからも仕事やその他のことにも集中して大事でいかなければいけません。
「ちょっと集中できなくなってくるな、少し身体を動かして集中力をまた備えて、きっと集中できるからまずストレッチでもするか」
そうやって自分でコントロールできるようになることは極めて大事なこと、子ども時代の親子の関わりで言われることは大きな財産になると私は考えています。
【まとめ】「ふざけている」ではなく「脳が求めている」
以上が、子どもが勉強に集中できません。 特に身体を動かしたり立ち上がりたいような素振りを見せるときの僕のオススメの対応です。
- 安全が椅子をガタガタしたり立ち歩いたりするのは、ふざけているのではなく、脳が集中状態を守るために「固有感覚」や「前庭感覚」を求めている生理的な反応。
- 親は動く禁止のではなく、「1分だけ動いて」など、時間をかけて体を動かすことを許可してあげるのが効果的です。
- この関わりは、子ども自身が「集中が切れたらどう対処するか」を学ぶ練習になり、将来の自立につながります。
どうしても原因はそれぞれなので、この対応が合う子に合わない子がいると思います。 ぜひ最初の方に試していただいて、皆さんのご家庭にとってより良い方法を見つけていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
幼児教育講師TERUでした。